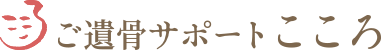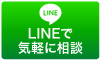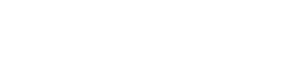ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
墓参りの意味とは?行くべき時期やマナー、注意点も解説
人はなぜお墓参りをするのでしょうか。忙しい日々の中でも、ふと「お墓参りに行かなきゃ」と思うのは、心のどこかに故人やご先祖様への感謝や祈りの気持ちがあるからかもしれません。
今回は、お墓参りをする意味から適切な時期、マナー、お墓参りができない時の対処法など、お墓参りにまつわるあれこれについて、詳しく解説します。
はじめてお墓参りをする方も、久しぶりに行こうと考えている方も、ぜひ参考にしてください。
お墓参りをする意味は「感謝」
お墓参りをするのは、亡くなった方に手を合わせるだけでなく、ご先祖様と、今生きている自分との繋がりに感謝することでもあります。
故人様の冥福を祈りご先祖様に感謝の気持ちを伝える
お墓参りは、亡くなった方の冥福を祈るとともに、私たちが今こうして生きていられることへの感謝を伝える、大切な機会です。
お墓の前で手を合わせるその行為には、敬意や感謝、そして供養の気持ちが込められています。
ご先祖様が代々つないできた命があるからこそ、今の自分たちが存在している。そんな当たり前のことに、改めて気づかされる瞬間でもあります。
今生きていることのありがたみを実感する
お墓のある場所は、日常とは少し距離のある静かな時間が流れています。忙しい日々から離れ、お墓の前で故人様に手を合わせると、「今を大切に生きよう」という気持ちが自然と芽生えるものです。
過去を偲び、今に目を向け、未来へつなぐ。お墓参りは、今を生きる自分自身と向き合う時間にもなるのです。
お墓参りの本当の意味は「心の対話」
お墓参りの本質は、形式的な儀式だけでは語れません。そこには、亡くなった方と心で語り合うような、静かな対話の時間があります。
「元気にしてるよ」「見守っていてね」そんな言葉を心の中で交わすことで、自分の気持ちが整理され、不思議と心が軽くなることもあるでしょう。
誰かに悩みを打ち明けるように、お墓の前で胸の内を伝えることが、心の安定につながるのです。
お墓参りをすると心が落ち着くのはなぜ?心理的な効果
お墓参りには、心理的な癒しの効果があるともいわれています。手を合わせ、深く呼吸をしながら祈ることで、自律神経が整い、心が穏やかになると考えられているのです。
自分という存在を再認識し、気持ちが穏やかになるということもあるでしょう。
心を整え、気持ちを切り替える「心のメンテナンス」としても、お墓参りは非常に有効です。
お墓参りをしないとよくないことが起こる?
「お墓参りをしないとバチが当たるのでは…」という声を耳にすることがあります。実際には、行かなかったからといって、何か悪いことが起きるということはありません。心配しなくても、大丈夫です。
ただし、自分自身の気持ちの中で、お墓参りができていないことへの気がかりが残っていると、それが不安やストレスの原因になることはあるでしょう。
お墓参りをしなくてもバチは当たりませんが、お墓参りには「心を整える」という側面があります。そう考えると、ときおり静かに手を合わせる時間を作ることは、自分の気持ちの安定のために、必要なことだといえます。
仏教以外のお墓参りの意味

仏教以外の宗教のお墓参りには、どのような意味があるのでしょうか。神道とキリスト教について、みてみましょう。
神道
日本では、お墓参りというと仏教のイメージが強いですが、神道にも祖先を敬い祀るという考え方があります。神道では「祖霊信仰」と呼ばれ、亡くなった方は家の守り神(祖霊)となって、家族を見守ってくれるとされています。
お墓は「奥津城(おくつき)」と呼ばれ、仏教のように線香をあげる習慣はなく、代わりに榊(さかき)を供えたり、玉串を奉げたりしてお参りします。
静かに手を合わせ、心からの感謝を伝える点は、仏教と共通しているともいえるでしょう。
キリスト教
キリスト教では「魂は天国に召される」という教義のもと、死後は神のもとで安らかに過ごしていると考えられています。
ですから、キリスト教のお墓参りは、仏教のように亡くなった方に手を合わせるのではなく、神に祈りを捧げるものです。
神に感謝し、故人様が天国で安らかに過ごせますようにと祈る儀式ですが、信仰の形は異なっても、故人を偲ぶ心は共通しています。
地域や家庭によって異なるお墓参りの習慣
お墓参りの方法やタイミングは、宗教だけでなく地域や家庭の慣習によっても大きく異なります。
たとえば、沖縄地方では「清明祭(シーミー)」という行事で親族が墓前に集まり、にぎやかに食事をともにしながら先祖を敬います。
また、北海道や東北地方では、春と秋のお彼岸よりも、お盆の墓参りが重視される傾向があるなど、地域性が色濃く反映されています。
さらに、家庭によっては「命日は家で静かに手を合わせるだけ」という場合もあれば、「できるだけ家族全員で墓前に集まるようにしている」というところもあるでしょう。
どの方法が正しい・間違っているということはなく、最も大切なのは、故人やご先祖様を思う気持ちを込めることです。
それぞれの家庭のやり方を大切にしながら、自分なりの形でお墓参りを続けていくことが、供養の本質に繋がっていくのです。
お墓参りに適した時期

基本的には、いつお墓参りをしても良いですが、いくつか適した節目があります。
お盆(7月13日~16日または8月13日~16日)
お墓参りの時期としてもっともなじみ深いのが「お盆」です。地域によって、7月に行う「新盆(しんぼん)」と、8月に行う「旧盆(きゅうぼん)」があります。
お盆は、先祖の霊が一時的にこの世に戻ってくるとされる時期で、家族そろってお墓を訪れ、迎え火や送り火を焚いて、お迎え・お見送りをするという風習が残っています。
最も多くの人が墓参に訪れる季節ともいえるでしょう。
お彼岸(3月・9月)
春分の日・秋分の日を中日とした7日間(彼岸の入りから彼岸明けまで)も、お墓参りに適した時期とされています。
仏教ではこの時期を「此岸(しがん/この世)」と「彼岸(ひがん/あの世)」がもっとも通じやすい期間とされ、ご先祖様に思いを届けやすいとされます。
お彼岸は季節の節目でもあるため、自然に感謝しながら心を整える機会としてもおすすめです。
故人様の命日
命日は、亡くなられた方を偲ぶ特別な日です。命日には2種類あり、1年に一度の命日を「祥月命日(しょうつきめいにち)」、毎月の同じ日を「月命日(つきめいにち)」と呼びます。
たとえば3月15日に亡くなった方であれば、毎年の3月15日が祥月命日、毎月の15日が月命日ということになります。
祥月命日はより丁寧な供養をする機会とされ、法要やお墓参りを行う家庭も多いです。月命日には仏壇に手を合わせたり、お花を供えたりすることで、日々の暮らしの中でも故人を思い出し続けることができます。
帰省したタイミング
遠方に住んでいて、頻繁にお墓参りができない場合は、帰省のタイミングを利用するのもひとつの方法です。
お盆やお彼岸に限らず、家族が集まった時に一緒にお墓を訪れることで、世代を超えたつながりや、ご先祖様への感謝を共有する機会にもなります。
年末年始、ゴールデンウィークなど長期休暇
年末年始やゴールデンウィークなど、まとまったお休みの時期も、お墓参りに適しています。
特に年末には「今年一年ありがとうございました」という気持ちで、年始には「新しい年もよろしくお願いします」というご挨拶の意味を込めて、お墓を訪れる人も多いです。
お墓参りに適した時間帯
一般的には、日が高いうち、つまり午前中から午後の明るい時間帯が望ましいとされています。これは安全面の配慮や、故人様を最優先にするという気遣いからですが、午後のお参りがいけないわけではありません。
最近では、それほど細かく時間帯を気にしなくても良い傾向がありますから、基本的には行ける時に行って構いません。
ただし、夕方以降に行く場合は、寺院や霊園の閉園時間を確認してから行った方が良いでしょう。
行きたいと思った時が良いタイミング
決まった時期に限らず、「ふと思い立った時」「あの人のことを思い出した時」こそが、お墓参りに最もふさわしいタイミングでしょう。
形式にとらわれすぎず、自分のペースで故人様と向き合うことが、心を込めた供養につながります。「行ける時に行く」「会いたい時に会いに行く」そんな自然な気持ちが大切です。
お墓参りをするときのマナー

お墓参りに行くときは、できるだけ準備をしてから行きたいものです。
お墓参りの時に準備していくもの
お墓参りには、いくつかの持ち物を事前に準備しておくとスムーズです。 基本的な持ち物は以下の通りです。
- 数珠(仏教の場合)
- 線香・ロウソク・マッチまたはライター
- お供え用の花
- お供物(果物・お菓子など)
- お掃除道具(ほうき、たわし、雑巾、バケツなど)
- ゴミ袋(使用後の線香の灰やお供物の包装を持ち帰るため)
掃除道具は現地で借りられる霊園もありますが、念のため簡単なものを持参しておくと安心です。
お墓参りの時の服装
服装に厳格な決まりはありませんが、落ち着いた色味の清潔な服装が基本です。
法事や命日など特別な日でなければ、カジュアルな服装でも構いませんが、派手すぎるデザインや露出の多い服装は避けた方がよいでしょう。
また、墓地は足場が悪いこともあるため、歩きやすい靴を選ぶのがおすすめです。
お供物のマナー
お供物としてよく選ばれるのは、果物・和菓子・故人様の好物などです。ただし、生ものや傷みやすい食品は避けた方が無難です。
動物が寄ってくる可能性があるため、お参り後は必ず持ち帰るのがマナーです。包装紙や袋も置きっぱなしにせず、持参したゴミ袋に入れて持ち帰りましょう。
お供えするのに適した花
仏花としてよく使われるのは、
- 菊
- カーネーション
- リンドウ
- スターチス
などの花です。
香りが強すぎないもの、トゲのないもの、毒性のないものが望ましいとされています。 故人が好きだった花を選ぶのも良い供養になりますが、バラなどのトゲのある花は避けるのが一般的です。
色合いは、白や淡い色を中心に、落ち着いた組み合わせがよいでしょう。
お墓参りをする順番
複数人でお墓参りをする場合は、全員で軽く一礼または合掌してから、故人と縁の深い方から順にお参りするのが一般的です。
血縁の近い順番、たとえば
- 配偶者
- 子ども
- 兄弟姉妹
などの順で手を合わせることが多く、礼を重んじる気持ちとして自然な流れとされています。
とくに厳密な決まりがあるわけではありませんが、年長者や目上の方を先にするなど、お互いに気持ちよく供養できるよう配慮することが大切です。
小さな子どもと一緒にお墓参りをするときの工夫
小さな子どもとお墓参りに行く際は、「静かにしなきゃダメ!」と厳しくするよりも、故人やご先祖様のお話をしてあげることがおすすめです。
「この人が○○ちゃんのおじいちゃんなんだよ」と伝えることで、命のつながりを感じるきっかけになります。
また、長時間じっとしていられない子もいるため、お参りの時間は短めにし、静かにできたら褒めてあげるなど、子どものペースに合わせてあげましょう。水遊びができないよう水桶や線香の火には十分注意してください。
お墓参りの作法

あまり厳密な決まりはありませんが、一般的には以下の流れでお参りをします。
お墓の掃除をする
お墓参りの最初のステップは、お墓をきれいに掃除することです。掃除を通して、故人やご先祖様への敬意を形にするという意味もあります。
まずは墓石や周囲に落ちている落ち葉やゴミを取り除き、草が生えていれば草取りも行います。墓石は水で濡らした雑巾やスポンジなどで優しく拭きましょう。
墓石に洗剤やブラシなどを使うのは避け、素材を傷めないように配慮してください。
墓前にある花立や線香皿、ロウソク立ても汚れがあれば一緒にきれいにします。これらの掃除を終えると、墓所全体が整い、気持ちも引き締まってきます。
お供えをしてお線香をあげる
掃除が終わったら、お花やお供物をお供えします。
次に、ロウソクに火を灯し、その火を使って線香に火をつけます。線香は火がついたら吹き消さず、手であおいで火を消すのが基本です。これは「口で息を吹きかけるのは不浄とされる」という仏教的な考えに基づいています。
線香を香炉に立てたら、墓前で静かに手を合わせ、祈りの気持ちを込めましょう。祈りの時間は長さよりも、心がこもっているかどうかが大切です。
ご先祖様や故人に「ありがとう」「また来ます」と語りかけるような気持ちで手を合わせると、自然と心が落ち着いてくるはずです。
お供えの後片付けをする
お参りが終わったら、お供えしたものは、基本的にすべて持ち帰るのがマナーです。
特に食べ物は、そのままにしておくと動物が来たり、他の墓地利用者に迷惑をかけたりすることがあります。花が枯れている場合は新しいものに替え、古いものは持ち帰りましょう。
また、線香の燃え残りやロウソクの残り、ゴミなどもきちんと片付け、来た時よりもきれいな状態でお墓をあとにすることが大切です。
これは、次に訪れる人や霊園管理の方々への配慮でもあり、気持ちのよい供養を締めくくる大事な作法でもあります。
お墓参りをする時の注意点

マナー違反だといわれないために、以下の点には注意をしてください。
ペットを連れていく時は寺院・霊園のルールに従うこと
家族の一員として可愛がっているペットを一緒に連れて行きたいと思う方も多いでしょう。しかし、お墓は故人を供養する神聖な場所ですから、寺院や霊園ごとに、ペットの立ち入りに関するルールが設けられている場合があります。
「敷地内はペット同伴禁止」「リード必須」など、そのルールを必ず事前に確認しましょう。
黙認されている場所であっても、周囲の方々への配慮を忘れず、静かに、迷惑にならないように行動することが大切です。
動物が苦手な人もいますから、抱っこやカートでの移動、糞尿の処理などを徹底しましょう。
周辺への配慮から静かに行動すること
お墓参りは、故人と静かに向き合う時間です。他の参拝者にとっても大切なひとときであることを忘れずに、静かで落ち着いた振る舞いを心がけましょう。
大きな声での会話や笑い声、走り回る子どもなどがトラブルのもとになることもあります。子ども連れの場合は、あらかじめ「ここは静かにする場所だよ」と教えてあげるのもよいでしょう。
ゴミはすべて持ち帰ること
お供えした花の包装紙、線香の燃え残り、ロウソクの芯、お菓子の包み紙など、お墓参りでは意外と多くのゴミが出ます。
霊園によってはゴミ箱が設置されていないこともあるため、必ずゴミ袋を持参し、すべて持ち帰るようにしましょう。
「来たときよりも美しく」を意識して帰ることで、自分自身の気持ちもすっきりと整います。次に訪れる方のために、そしてご先祖様への敬意としても、片付けまでを丁寧に行うことが供養の一環です。
どうしてもお墓参りができない時は

お墓参りをしたいけどできない、そんなときは、今できる範囲で、供養の気持ちを表すだけでも十分です。
お墓参りは義務じゃない?現代のライフスタイルとの向き合い方
- 遠方にお墓がある
- 仕事や家庭の事情で時間が取れない
- 体調がすぐれない
など、お墓参りに行きたくても行けない事情は人それぞれです。
大切なのは、「行けないこと」に罪悪感を持つのではなく、今の自分にできるかたちで供養する気持ちを大切にすることです。
現代はライフスタイルが多様化しており、お墓との距離感も人によって異なります。昔ながらの形にこだわるよりも、無理なく心を寄せる方法を選ぶことが、自然な供養のあり方ではないでしょうか。
最近増えている「オンライン墓参り」とは
最近は、墓地に行かずに供養ができる「オンライン墓参り」という方法も注目されています。
コロナ禍で普及してきたスタイルで、実際のお墓の画像に手を合わせたり、デジタルのお墓(バーチャル霊園)にお参りしたりします。
霊園スタッフなどが代行でお墓の清掃やお参りを行い、その様子を写真や動画で送ってくれるサービスもあり、遠方に住んでいる方や、高齢で外出が難しい方などに利用されています。
形は違っても、故人様に「心を寄せる」という本質は同じです。時代に合った供養のあり方として、今後さらに広まっていくでしょう。
自分なりに故人様やご先祖様に感謝の気持ちを伝える
お墓に行かなくても、日々の中でふと故人のことを思い出し、「ありがとう」と心の中で語りかけるだけでも、立派な供養になります。
仏壇に手を合わせたり、故人が好きだった食べ物を思い出して、食卓に並べたりすることもひとつの方法です。手紙を書いたり、心の中で話しかけたりと、自分なりのスタイルで感謝の気持ちを伝えることが大切です。
大切なのは形ではなく供養する気持ち
お墓参りにはさまざまなかたちがありますが、最も大切なのは「こうしなければならない」という形式ではなく、どんな方法であっても心から供養したいという気持ちです。
行けない時に無理をするよりも、「また行ける時に行こう」「今は心の中で語りかけよう」と、穏やかに自分の気持ちと向き合うことで、自然と心が落ち着いてくるはずです。
形式にとらわれすぎず、自分らしくご先祖様と向き合える方法を見つけていきましょう。
まとめ
お墓参りは、故人様やご先祖様に感謝の気持ちを伝える大切な時間です。形式や決まりごとにとらわれすぎず、「今ここに生きている自分」が何を思い、どんなふうに手を合わせたいのか、その気持ちが何よりも大切です。
お盆やお彼岸、命日だけでなく、思い立った時に訪れるのも立派な供養です。遠方でどうしても行けない場合も、心の中で語りかけることが、その人らしい供養になるでしょう。
大切なのは、「手を合わせよう」と思える気持ちと、静かに心を向ける姿勢です。お墓参りは亡き人との対話であり、自分自身を見つめ直す機会でもあります。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。