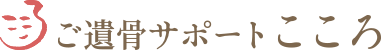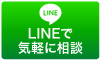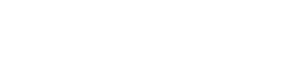ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
永代供養は法事をしなくていい?年忌法要の対応や費用の相場について解説
永代供養は、ご遺骨を寺院や霊園に預け、その施設が続く限り供養を続けてもらうという供養の方法です。自分たちで墓地の管理をする必要がなく、費用も一定で済むことから、近年注目を集めています。
しかし、永代供養を選ぶ際に気になるのが、法事との関係です。
「永代供養にしたから、三回忌などの年忌法要はしなくて良いの?」「そもそも、法事とは何をするものなの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
そこで今回は、永代供養と法事の関係について、詳しく解説していきます。三回忌以降の年忌法要が必要かどうか、行う場合の手順や費用、準備するものなど、気になる点についてご紹介します。
Contents
永代供養の基本
永代供養とは、故人様の遺骨を一定期間もしくは永続的に寺院や霊園が管理してくれる供養の方法です。
お墓を管理する後継者がいない場合や、家族に負担をかけたくないと考える方々に選ばれることが多いです。
永代供養は、一般的に合同墓や合葬墓、樹木葬などの形式で行われることが多く、寺院や霊園が責任を持って供養を行います。
個別墓の形もありますが、それでは費用の面で普通にお墓を建てるのとあまり変わりなく、100万円~300万円ほどかかることもあります。
個別に供養していただく場合であっても、未来永劫管理してもらえるわけではなく、三十三回忌など節目に当たるタイミングで合祀されることがほとんどです。
永代供養にすれば必ずしも法事をしなくても良い

結論からいいますと、永代供養はお寺や霊園が普段から供養してくれていますから、法事をする必要はありません。
特に、お彼岸やお盆など、一般的な仏教行事については、寺院や霊園が合同で供養を行ってくれる場合が多いです。
遠方でお墓参りができなかったり、家族が集まるのが難しかったりしても、お寺がしっかり供養してくれますから、安心してください。
永代供養にした場合の法事は家族の気持ち次第
永代供養にすれば年忌法要を行わなくても問題はありません。
しかし、故人様を偲び、冥福を祈りたいという気持ちから、法事を執り行うことはもちろん可能です。いつでも、自由に法事を行うことができます。
家族でよく話し合い、故人様を偲んで法要を行いたいとなれば、お寺と相談の上、日程などを決めると良いでしょう。
法事を行うことは追善供養にもなる
追善供養とは、故人様の冥福を祈り、その魂が安らかに過ごせるように行う供養のことです。
「追善」という言葉は、「善行を追う」という意味があります。つまり、故人が生前に行った善行をさらに積み重ねることで、その魂がより良い世界に導かれるように祈る行為です。
また、故人様を偲ぶことで、生きている者たちが故人とのつながりを再確認し、故人様の教えや思い出を大切にする良い機会ともなります。
追善供養は、故人様を思い続ける心の表れであり、仏教的な教えに基づいた大切な供養の一環です。
一般的には、命日や、四十九日、一周忌、三回忌などの年忌法要で行われます。
法事は家族が集まる良い機会でもある
法要を行う際は、普段一緒に住んでいる家族だけでなく、親戚にも声をかけるでしょう。
故人様を通して、普段顔を合わせることのない親戚同士が集まり、共に故人様を偲ぶ良い機会となります。
お互いに近況報告をしながら、親睦を深めるのも良いでしょう。
永代供養で追善供養を行う主なタイミング

一般的には、以下のようなタイミングで追善供養を行います。
納骨の時
納骨とは、お墓にご遺骨を埋葬することです。 納骨するときの法要を納骨式といいますが、タイミングについては特に決まりがありません。
火葬後すぐに行う人もいれば、四十九日のタイミングで行う人もいます。 既にお墓が準備してあればいつでも可能ですが、なくなってから探すとなると時間がかかるため、タイミングの良い四十九日で行う人が多いです。
月命日の法要
命日の法要はお寺や霊園がやってくれるはずですので、追善供養として行うなら月命日の法要をお願いします。
亡くなった月を除き、11回の法要を行うことができます。
年忌法要
<主な年忌法要>
- 一周忌
- 三回忌
- 七回忌
- 十三回忌
- 十七回忌
- 二十三回忌
- 二十七回忌
- 三十三回忌
- 五十回忌
なかでも、一周忌と三回忌は、重視されている法要です。一周忌は、故人がこの世を去ってから最初の節目であり、冥福を祈り、供養の気持ちを新たにする大切な機会です。
三回忌は、一周忌の後に続く重要な節目であり、故人の霊が安らかに生まれ変われるよう、さらに深い供養を行うと考えられています。
たくさんの親戚や場合によっては友人や知人などを招いて、大きな法要を行う人が多いです。
ただし、法要はあくまで気持ちで行うものであり、 最初に説明した通り、 永代供養をしていれば無理に年忌法要を行う必要はありません。
また、三回忌までは行い、それ以降はお寺にお任せするという人も多いです。
お盆
お盆は8月の中旬に、ご先祖様を家に迎え供養する、日本の伝統的な行事です。正式名称を「盂蘭盆会(うらぼんえ)」といい、一般的には8月13日から16日にかけて行われますが、地域によって時期が異なることもあります。
ご先祖様の霊が迷わず家に戻ってこられるように、玄関先に迎え火を焚き、ご飯、お供え物、飲み物などを供えます。
お盆の最終日には、ご先祖様の霊が安らかにあの世へ帰れるように、送り火を焚きます。
お盆は、家族が帰省しやすい時期でもあります。この時期に親戚が集まり、 法要を行うのも良いでしょう。
お彼岸
春分の日・秋分の日に、それぞれお彼岸の法要を行う場合があります。 この前後3日間を合わせた合計7日間を、「春のお彼岸」「秋のお彼岸」とそれぞれ呼んでいます。
お彼岸は、仏教行事というよりも、暮らしの中に溶け込んでいる風習のひとつとなっています。
1週間と期間も長いので、親戚も集まりやすいのではないでしょうか。
永代供養で法事を執り行いたい場合の流れ
永代供養で法事を行う場合、以下のような流れで進めていきます。
どの法要を行うか決める
故人の命日や、四十九日、一周忌、三回忌など、法要を行う日時を決めましょう。どの法事を行うかは、宗派や家族の考え方によって異なります。
家族や親戚と相談しながら決めることをおすすめします。
寺院や霊園に相談する
まずは、ご遺骨を預けている寺院や霊園に相談しましょう。法事を行う際の注意点や、必要な手続きについて教えてもらえます。
こちらの一方的な都合で日程を決めてから相談しても、僧侶の都合が合わない可能性があります。 日程決めと並行して、僧侶の手配をします。なじみの僧侶がいない場合は、永代供養を行っている寺院や霊園に相談してみてください。
親戚への連絡や供物の準備
親族や友人など、参列者に日時や場所を連絡します。
また、同時に法要に必要な供物やお花を用意しましょう。
会食会場の手配も必要ですが、どのような場所で行わなければならないか、特に決まりはありません。
集まってくれる親戚の人数によっても適した場所が違ってくるでしょう。参列してくれる方の年代なども考慮し、みんなが利用しやすいお店を選びます。
追善供養のお布施
三回忌や年忌法要を行う場合は、その際のお布施が必要になります。
お布施の相場は地域や寺院によって異なりますが、一般的には30,000円~50,000円程度が目安です。お布施はあくまで感謝の気持ちを示すものです。これまでのお寺との関係性などもありますので、金額で迷ったら直接聞いてみても大丈夫です。
さすがに、「お布施の金額はいくらですか」とは聞きづらいと思います。その場合は、「皆様おいくらくらいお持ちになっていますか」と聞いてみてください。
また、僧侶を自宅や霊園に招いて法要を行う場合には、交通費やお膳料として追加の費用がかかることもあります。「お車代」として5,000円程度、会食に参加されない場合は「御膳料」として5,000円~10,000円程度お渡しします。
永代供養にかかる費用の相場

永代供養を行う際には、最初に「永代供養料」として費用が発生します。
この永代供養料は、供養の期間や墓の形式によって異なりますが、一般的には5万円から100万円程度です。この費用には、永代にわたる供養や管理が含まれているため、追加の費用は基本的には発生しません。
- 合祀墓:他のご遺骨と一緒に埋葬するタイプで比較的費用が安く、5万円~30万円程度が相場
- 集合墓:個別のスペースに納骨するタイプで、10万円~30万円程度が相場
- 個別墓:個人の墓石を建てるタイプで、100万円以上かかる場合もある
合祀墓や集合墓であれば、個別にお墓を建てるのと比較すると、かなり費用を安く抑えられます。
まとめ
永代供養は、家族に負担をかけず、故人様を供養するための便利な方法です。お寺や霊園が供養をしてくれていますので、法事については必ずしも行う必要はありません。
しかし、故人様を偲び、冥福を祈りたいという気持ちから、法事を執り行いたいと考える方も少なくありません。
永代供養で法事をする場合は、事前に寺院や霊園に相談し、手順や費用についてよく確認しましょう。
供養の心を忘れずに、家族と故人の絆を大切にしていきたいものです。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。