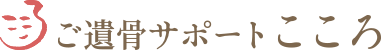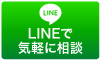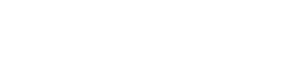ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
お墓を継ぐ人がいないときの解決策とは?後継者なしでも安心できる供養方法
少子高齢化や核家族化の影響で、「お墓を継ぐ人がいない」という悩みを抱える方が増えています。
両親や祖父母のお墓を誰が引き継ぐのか、また自分のお墓はどうするのか。身寄りが少なくなった現代では、多くの人が直面する問題です。
お墓を継ぐ人がいないまま放置すれば、無縁墓として撤去されてしまう可能性もあります。 しかし、必ずしも慌ててお墓を建てたり、承継者を探したりする必要はありません。
墓じまいや永代供養、樹木葬や散骨など、後継者がいなくても、安心できる供養方法はいくつもあります。
そこで今回は、お墓を継ぐ人がいない場合に何が起きるのか、お墓を管理できない場合の具体的な対処法などについて、詳しく解説します。自分や家族のお墓について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
お墓を継ぐ人がいない現状と背景
なぜ、お墓を継ぐ人がいないのか、それには以下のような理由が考えられます。
晩婚化・少子化による後継者不足
近年、日本では晩婚化や少子化が進み、子どもの人数自体が減少しています。
かつては、家督を継ぐ長男や地元に残る子どもが、自然とお墓を引き継ぐことが多かったのですが、今は事情が大きく変わりました。
結婚や出産を選ばない人も増え、子どもがいない家庭ではそもそもお墓の後継者が存在しません。
また、子どもがいても遠方に暮らしていたり、仕事や家庭の事情で、地元のお墓を守ることが難しいケースも少なくありません。その結果、将来的に「お墓を継ぐ人がいない」状況になる世帯が急増しています。
核家族化で地方のお墓を継ぐ人がいない
さらに、核家族化も大きな要因です。戦後の高度経済成長期以降、多くの人が仕事を求めて都市部へ移住し、親世代とは別に生活をするようになりました。
地方の実家にあるお墓は、都会に暮らす子どもや孫にとって物理的にも心理的にも「遠い存在」になりがちです。
お盆や命日に帰省することはあっても、日常的な管理や掃除、寺院へのお布施などを継続的に行うのは、大きな負担になるでしょう。
こうした背景から、親族間で「誰が継ぐのか」が決まらないまま時間が経ち、最終的に無縁墓となってしまうお墓も増えているのです。
お墓を継ぐ人がいない場合に起きる問題

ではお墓を継ぐ人がいないと、どうなるのでしょうか。誰も管理せずに放置されたお墓は、最終的には撤去されてしまう可能性があります。
お墓が荒れて無縁墓になる
お墓を管理する人がいなくなると、草木が伸び放題になり、墓石も苔や土埃で覆われ、見た目にも荒れていきます。
寺院や霊園によっては、簡単な清掃をしてくれるところもありますが、あくまで敷地全体の管理であり、個別の墓石やお供え物の片付けまでは行われません。
この状態が続くと、管理者は「このお墓は長期間放置されている」と判断します。管理料の滞納が数年続いた場合、寺院や霊園は契約者やその親族に通知や督促状を送付します。
それでも連絡がつかない、または支払い・管理がされない場合、管理者は墓地の掲示板や自治体の広報誌に「無縁墓に該当する可能性がある旨の公告」を行います。
この公告期間は、自治体や霊園によって異なりますが、一般的には1年間前後です。その間に管理者や親族からの申し出がなければ、正式に「無縁墓」として扱われます。
お墓を継ぐ人がいないと最終的には撤去されてしまう
無縁墓と認定された後は、墓石が撤去され、遺骨は合祀墓(共同墓)や納骨堂に移され、他の方の遺骨と一緒に供養される形となります。
一度この手続きが完了すると、元の個別墓に戻すことも、遺骨を取り出すこともできません。また、合祀墓に移された後は、個別に遺骨を取り出すこともできないため、家族や親族にとって精神的な喪失感が大きいケースもあります。
こうした事態を避けるためには、後継者がいない場合でも、早めに墓じまいや永代供養などの方法を検討し、計画的に動くことが大切です。
お墓を継ぐのは長男でなくても可能
お墓は、誰が承継しても良いものです。
生前の指定で後継者を決められる
かつては「長男がお墓を継ぐ」という考え方が一般的でしたが、現在の法律や慣習では必ずしもそうではありません。
お墓の管理や承継は、被相続人(お墓の名義人)や祭祀主宰者が、生前に誰を後継者とするかを自由に指定できます。
たとえば、長女や次男、さらには血縁のない養子、親しい友人を後継者とすることも可能です。
ただし、後継者を指定する場合は、遺言書や契約書などの書面で明示しておくと、後のトラブルを防げます。
特に寺院墓地では、後継者の氏名を事前に届け出ておく必要がある場合がありますので、早めに確認しておきましょう。
姓が変わっていても承継できる
結婚や養子縁組などで姓が変わっていても、お墓の承継は可能です。法律上、姓の一致は承継条件ではなく、血縁関係や名義人の意思が優先されます。
たとえば、結婚後に姓が変わった娘が実家のお墓を継ぐこともできますし、養子として迎え入れた方が継ぐこともできます。
ただし、寺院や霊園によっては、戸籍や住民票など、血縁や関係性を証明する書類の提出を求められることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
親族で話し合って決定してもかまわない
後継者が生前に指定されていない場合は、親族間で話し合い、お墓を継ぐ人を決めることができます。
必ずしも直系の子どもである必要はなく、甥や姪、いとこなどが承継者となるケースもあります。
このとき重要なのは、全員が納得した上で決めることです。
後から「聞いていなかった」「勝手に決められた」といったトラブルにならないよう、話し合いの内容をメモや書面に残しておくと安心です。
また、後継者が決まったら、速やかに寺院や霊園へ連絡し、名義変更や契約者の変更手続きを行いましょう。
お墓を継ぐ人がいない場合、これから新たなお墓を建てるのは難しい
お墓は本来、代々受け継いでいくことを前提で建立されています。
そのため、最初から「後継者がいない」とわかっている場合、寺院や霊園が新たなお墓の契約を認めないことが多くあります。
特に寺院墓地では、檀家として継続的に供養や管理を行うことが条件となるため、後を継ぐ人がいない状態では契約が難しいのが実情です。
仮に契約できたとしても、将来的に無縁墓となるリスクが高く、霊園側からもあまり勧められません。
このような背景から、後継者がいない場合は、個別墓ではなく永代供養墓や樹木葬など、承継を前提としない供養方法を選ぶようが良いでしょう。
お墓を継ぐ人がいない時の対処法

では、お墓を継ぐ人がいない場合、無縁墓にしないためにはどうすれば良いのでしょうか。
管理費を前納して維持する
後継者がいない場合でも、一定期間はお墓を維持する方法があります。それが、寺院や霊園に管理費を一括前納する方法です。
前納期間は、施設によって異なりますが、10年・20年といった長期契約が可能なところもあります。
契約期間中は、寺院や霊園が草刈りや敷地管理を行ってくれるため、離れて暮らしていてもお墓が荒れる心配が少なくなるでしょう。
ただし、契約期間が終了すれば、お墓は無縁墓として扱われ、合祀墓に移されるのが一般的です。「いずれは墓じまいになる」ことを前提に、一時的な維持策として利用するのがおすすめです。
墓じまいをして供養方法を変える
後継者がいない場合、墓じまいも検討しましょう。墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、遺骨を別の供養方法に移すことをいいます。
墓じまいを行うことで、将来的に無縁墓になる心配がなくなり、管理費や清掃などの負担からも解放されます。
遺骨の移し先としては、永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養などがあり、いずれも継承者が不要な供養方法ます。
墓じまいは費用や手続きの負担がある一方で、後の世代に迷惑をかけずに済む方法であるため、早めに検討する方も増えています。
お墓を継ぐ人がいない時の墓じまいのメリット
墓じまいをすることに抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、以下のようなメリットがあります。
お墓の管理の手間・費用がなくなる
お墓を維持するには、定期的な清掃や草取り、法要の準備など、手間と時間がかかります。さらに寺院や霊園への管理費、法要やお布施などの費用も継続的に必要です。
墓じまいを行えば、こうした日常的な管理の負担と出費が一切不要になります。
特に、遠方に住んでいる場合や、高齢になってからの管理は体力的にも難しくなるため、早めの墓じまいをおすすめします。
無縁墓として撤去されるのを防ぐ
後継者がいないままお墓を放置すると、いずれ無縁墓と認定され、遺骨が合祀墓へ移されてしまいます。
撤去となると、事前に合祀先や供養の方法を選ぶことができず、形式的な合祀供養になってしまうケースもあります。
墓じまいを行えば、自分や家族の意志で永代供養や樹木葬など、希望に沿った供養方法を選べるため、納得のいく形で大切な遺骨を守ることができます。
つまり、墓じまいは単なる撤去ではなく、「自分たちで供養のかたちを決める」ための前向きな選択ともいえるのです。
墓じまいをした後の供養の方法

墓じまいをした後は、管理の手間が少ない方法を選ぶと、無理なく供養を続けていけます。
永代供養
永代供養とは、寺院や霊園が遺骨を長期間、または契約期間満了まで供養してくれる方法です。
多くの場合、一定期間(33回忌までなど)は個別に安置し、その後合祀墓へ移されます。
<メリット>
- 後継者が不要で、管理もすべて施設が行ってくれる
- お参りの際は施設を訪れるだけでよい
- 宗派を問わず受け入れてくれる場合が多い
<デメリット>
- 契約期間終了後は合祀されるため、個別の墓は残らない
- 埋葬場所を自由に選べない場合がある
散骨
散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などの自然に撒く供養方法です。
法律上は節度をもって行うことが求められ、専門業者に依頼するケースがほとんどです。
<メリット>
- 管理や維持費が一切かからない
- 自然に還るという考え方に共感する人が多い
<デメリット>
- 散骨後は遺骨を回収できない
- 一部の親族が心理的に受け入れにくい場合がある
- 法律や自治体のルールに配慮が必要
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木や花を墓標として埋葬する方法です。
専用の庭園や山林に遺骨を埋葬し、その上に木や花を植えることが一般的です。
<メリット>
- 自然に囲まれた環境で眠れる
- 墓石がないため費用が比較的安い
- 永代供養型を選べば後継者不要
<デメリット>
- 埋葬場所が都市部から遠いことが多い
- 樹木や花は永遠に残るわけではない
- 区画や埋葬方法が施設の規定に従う必要がある
手元供養
手元供養は、遺骨や遺灰の一部を自宅で保管し、日常的に故人を偲ぶ方法です。
専用の骨壺やペンダントなどに納めて保管します。
<メリット>
- 常に故人を身近に感じられる
- 自宅で気軽にお参りできる
- 遺骨の一部だけを手元に置き、残りは他の供養方法と組み合わせることも可能
<デメリット>
- 保管中の破損や紛失リスクがある
- 現在供養している人がいなくなったときにどうするかを決めておかなければならない
- 宗教観によっては受け入れにくい場合がある
墓じまいの流れと費用

墓じまいすることを決めたあとの、実際の流れについて説明します。
親族と相談して墓じまい後の供養の方法を決める
墓じまいを始める前に、まずは親族間での合意形成が重要です。墓じまいは感情的な問題を伴いやすく、「知らないうちに撤去された」というトラブルも珍しくありません。
永代供養や樹木葬、散骨など、遺骨の移し先についても早めに意見をすり合わせましょう。
菩提寺、石材店に相談する
菩提寺がある場合は、必ず事前に相談します。寺院墓地では檀家であることが前提のため、墓じまいの理由や、今後の供養方針を丁寧に説明することが大切です。
また、墓石の撤去は石材店に依頼しますが、多くの場合、寺院や霊園が指定業者を持っています。自分が依頼したい石材店を選べるかどうかは、寺院次第です。
必要書類(埋葬証明書・改葬許可証)を揃える
墓じまいには、主に以下の書類が必要です。
- 埋葬証明書(現在の墓地管理者が発行)
- 改葬許可証(新しい埋葬先を管轄する役所で発行)
改葬許可証は、遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合に必要となります。一方で、散骨や手元供養にする場合は、改葬許可証が不要となるケースもあります。
書類の不備があると手続きが進まないため、石材店や新しい埋葬先にも確認しながら進めると安心です。
閉眼供養をして墓じまいをする
撤去前には、僧侶による閉眼供養(魂抜き)を行います。これは、墓石に宿るとされる故人の魂を抜き、感謝とお別れをする儀式です。
閉眼供養は仏式では一般的ですが、宗派や地域によって呼び方や手順が異なる場合があります。この際のお布施は、3万~5万円程度が相場です。
寺院によっては、別途交通費(お車代)や、御膳料を包む場合もあります。
金額の目安はあくまで相場であり、菩提寺や僧侶との関係性によって変わるため、事前に確認しておくと安心です。親戚と相談するか、もしわかる人がいなければ、寺院に直接聞いても問題ありません。
閉眼供養後に墓石を撤去し、遺骨を新しい供養先へ移します。
墓じまいの費用の相場
墓じまいの費用は、お墓の大きさや立地によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 項目 | 費用目安 |
| 墓石撤去・処分 | 1㎡あたり5万~10万円 |
| 改葬許可申請など書類手続き | 数千円~ |
| 遺骨の移送・新しい供養費用 | 永代供養:5万~50万円
樹木葬:20万~50万円 散骨:5万~20万円 |
トータルでは30万円~100万円程度になることが多く、特に地方から都市部の霊園へ移す場合は費用が高くなります。
見積もりは必ず複数の石材店から取り、比較検討することをおすすめします。
お墓の承継でトラブルを起こさないために

お墓の承継は、感情や価値観が絡むため、放置すると親族間のトラブルに発展しやすい問題です。
特に後継者がいない場合、誰が管理するのか、次にどの供養方法を選ぶのかが曖昧なままだと、いざというときに意思決定ができず、結果として無縁墓化してしまう恐れがあります。
そのため、できるだけ早い段階で親族全員が集まり、将来の方針を話し合っておくことが重要です。
可能であれば、話し合いの内容をメモや書面に残し、全員で共有しておきましょう。
こうすることで、後から「聞いていなかった」「勝手に決められた」という誤解を防げます。
また、生前に承継者や供養方法を決めておくことで、遺された家族の精神的・経済的負担を大きく減らすことができます。
まとめ
少子高齢化や核家族化の影響で、「お墓を継ぐ人がいない」という問題は、もはや珍しいことではありません。
後継者がいないまま放置すると、お墓は無縁墓となり、撤去・合祀されてしまいます。一度撤去されてしまうと、元には戻せず、遺骨を取り出すこともできません。
重要なのは、できるだけ早く動き出すことです。
どうしても後継者が決まらない場合は、管理費の前納や墓じまいなど、現実的な対策が必要です。墓じまい後は、永代供養・樹木葬・散骨・手元供養など、継承者不要の方法を選べば、将来的な心配を減らせます。
早めの準備が、家族の負担を減らし、大切な人の供養を守ることにつながります。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。