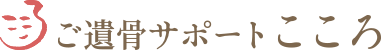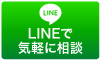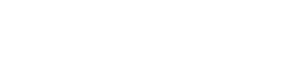ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
納骨しないで家に置くのはアリ?遺骨を家で供養する方法
近年、ご遺骨をご自宅に置いたまま、納骨をせずに供養するという選択をする方が増えています。「お墓がない」「すぐに気持ちの整理がつかない」「家族と離したくない」などさまざまな事情や思いがあるなかで、「納骨しない」という選択は、決して珍しいものではなくなってきました。
とはいえ、「自宅に遺骨を置いても大丈夫?」「法律にふれないの?」「親族に反対されたらどうしよう」といった不安を抱える方も少なくありません。
そこで今回は、納骨せずにご遺骨を家に置くことは可能なのか、どんな供養の方法があるのか、注意すべき点や心構えについて、わかりやすく解説していきます。
Contents
ご遺骨を納骨しないで家に置くことは問題ない
ご遺骨はお墓に納骨しなくても、何ら問題はありません。
家に置くことは法的に問題ない
ご遺骨を自宅に保管すること自体は、法律上まったく問題ありません。日本の法律では「遺骨を自宅で保管してはいけない」という明確な禁止規定はなく、火葬後の遺骨を個人で管理することも認められています。
ただし、ご遺骨を庭に埋めたり、勝手に他人の土地に埋葬したりする行為は「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触する可能性があるため注意が必要です。
お墓を建てずに供養する人も増えている
核家族化やライフスタイルの変化、経済的な事情、また宗教観の多様化などにより、「お墓を建てずに自宅で供養する」というスタイルを選ぶ人が増えてきました。
特に都市部ではお墓の維持や距離の問題もあり、ご遺骨を家で供養することが、心の安らぎにつながるケースも多く見られます。ミニ仏壇や写真と一緒に遺骨を置くなど、故人を身近に感じながら、日常の中で手を合わせられる点も選ばれる理由のひとつです。
ご遺骨を庭に埋めるのはNG
一方で、遺骨を庭に埋めることは基本的にできません。たとえ自分の所有する土地であっても、墓地としての認可を受けていない場所に遺骨を埋める行為は、「埋葬」ではなく「遺体の遺棄」とみなされる可能性があるのです。
どうしても庭などに埋葬したい場合は、自治体や保健所などの関係機関に事前相談し、ご遺骨をパウダー状にしてから散骨するならできるかもしれません。
納骨しないと良くないといわれる理由

納骨しなくても全く問題はありませんが、良くないとされているのには、このような理由が考えられます。
納骨しないと成仏できないという誤解
「納骨をしないと成仏できない」「いつまでも遺骨を家に置いておくのは故人が迷う原因になる」といった話を耳にすることがあります。これは宗教的な考え方に基づいたものであり、必ずしもすべての宗派や価値観に共通するものではありません。
そもそも仏教のなかでも「納骨=成仏」という明確な教義は存在せず、納骨は、故人様を弔うための儀式であって、成仏するかどうかとは関係ないのです。
供養の形は人それぞれ。大切なのは形式よりも、故人を思い、心を込めて手を合わせる気持ちです。納骨の有無だけで、成仏できるか否かが決まるわけではないということを、知っておくと心が軽くなるかもしれません。
遺骨が身近にあるという抵抗感
ご遺骨を家に置くことに抵抗を感じる方も少なくありません。たとえば、「亡くなった人の気配を日常に感じてしまってつらい」「なんとなく落ち着かない」という心理的な理由から、自宅での保管を避けたいという意見もあります。
また、親族のなかで考え方が分かれることも多く、意見の相違によるトラブルに発展することもあります。こうした場合は、無理に一人で決断せず、家族や親戚としっかり話し合い、思いを共有しながら納得のいく形を探ることが大切です。
ご遺骨を家に置く理由は人それぞれ
納骨せずに、ご遺骨を家に置くのは、人によって様々な理由があります。
お墓の費用負担が難しい
お墓を建てる、あるいは購入するには数十万円から数百万円の費用がかかることもあり、経済的な事情からすぐに納骨できないという方もいます。
また、墓地の管理費や法要の費用も継続的にかかるため、「無理をしてお墓を持つより、身近で供養したい」と考えるのは自然なことです。
気持ちの整理がつかない
大切な人を亡くしたばかりで、心の整理がつかない状態では「お墓に納める=完全に別れたように感じる」と思う方も多くいらっしゃいます。
そんなとき、無理に納骨を急ぐ必要はありません。手元にご遺骨があることで、心が落ち着くまでゆっくり向き合える時間を持てるというのも、ご遺族の大切な癒しとなります。
家族と離れたくない
「これまで一緒に過ごしてきた家族と、突然物理的にも離れてしまうのがつらい」「もう少し一緒にいたい」そう感じることも、ごく自然な感情です。
とくに長年連れ添った配偶者を亡くした方や、親を見送った子ども世代の方などに多く見られます。遺骨がそばにあることで、心の支えとなる場合もあるのです。
お墓に入れたくない宗教・信条的理由
宗教観や価値観の変化も、納骨しない理由のひとつです。伝統的な供養スタイルにこだわらず、自分なりの方法で故人を大切にしたいという思いから、お墓に入れずに自宅で供養する方もいます。
また、「無宗教だから墓という形にこだわらない」「死後も自由であってほしい」という思いを持つ方も増えています。
納骨しないで家に置く選択をしたあとの流れ
それでは、納骨しないでご遺骨を家に置く選択をしたときに、考えておくべきことについてまとめました。
どこに置くか(居間・寝室・仏間など)
ご遺骨を家に安置する場合、まずは置く場所を決めましょう。仏間があるご家庭なら、仏壇とともに祀るのが一般的ですが、必ずしも仏間でなければならないわけではありません。
たとえば居間の一角や寝室に、写真やお花と一緒に安置するケースも増えています。大切なのは、そこが心が落ち着く場所、手を合わせやすい場所であることです。
誰が管理するかを明確にする
ご遺骨をご自宅で保管する場合、その後の管理をどうするかを決めておくことが大切です。
とくに家族が複数いる場合、
- 誰が管理するのか
- 万が一引っ越すときはどうするか
- 管理している人が亡くなったらどうするか
などを話し合っておくと安心です。
将来、代替わりや介護、相続などの節目でトラブルが起きないように、記録に残しておくのもひとつの方法です。
将来納骨・散骨したくなった場合は?
今は家で供養したいと思っていても、将来的に「お墓に納骨したい」「散骨したい」と考えることもあるかもしれません。そうした場合に備えて、ご遺骨をきちんと保管し、風化や破損を防ぐよう心がけておきましょう。
また、宗教施設や散骨業者などに事前相談しておくことで、スムーズに移行できる可能性も高まります。「いま」と「いつか」の両方に目を向けておくことが、家族全体の安心にもつながります。
納骨しないで家に置く供養の方法

納骨しないで、遺骨を家に置く場合の、供養の方法をご紹介します。
ミニ仏壇に安置する
最近では、家具調やインテリアに馴染むデザインのミニ仏壇が人気です。小さな台の上にご遺骨と写真、お花やお線香を置いて、心静かに手を合わせられる空間をつくることができます。
場所を取りませんし、大がかりな準備をしなくても、気軽に始められる供養の形として注目されています。
ご遺骨を供養するスペースを作る
必ずしも仏壇でなくても、リビングの一角や寝室などに「供養スペース」を設ける方法もあります。写真や思い出の品、ご遺骨を納めた骨壺を飾ることで、自分だけの祈りの場所ができあがります。
お花を添えたり、好きだった音楽を流したりすることで、より心のこもった供養が可能になります。
ご遺骨をプレートに加工する
ご遺骨の一部を特殊な加工でプレートやセラミックにし、飾れる形にする供養方法もあります。コンパクトで場所をとらず、インテリアとしても違和感がないため、現代のライフスタイルに合った新しい形の供養として選ばれています。
加工には専門業者の依頼が必要ですが、仕上がりの美しさや扱いやすさが魅力です。
アクセサリーにして身につける
大切な人をいつもそばに感じていたいという思いから、ご遺骨の一部をペンダントやブレスレットに加工して身につける「メモリアルジュエリー」も人気です。
遺骨の粉末を樹脂や金属に閉じ込めることで、見た目には普通のアクセサリーと変わらず、外出先でも一緒にいられる安心感があります。心のよりどころとして、多くの人に選ばれています。
ご遺骨を納骨せずに家に置くときの注意

納骨せずに家にご遺骨を置く場合は、以下の点に注意してください。
家族・親戚とよく話し合うこと
ご遺骨を家に置くことは個人の自由ですが、家族や親戚の理解と協力があってこそ、安心して供養を続けることができます。
「なぜ家に置いておきたいのか」「いつまで置くつもりなのか」など、思いをきちんと共有し、誤解や不信感を避けることが大切です。とくに今後、別の場所への移動や納骨を考える可能性がある場合は、早めに話し合っておくとよいでしょう。
ご遺骨が破損しないよう注意すること
骨壺は陶器やガラス製のものが多く、落下や衝撃により破損するおそれがあります。お子さまやペットがいるご家庭では特に注意が必要です。
転倒防止のため、滑り止めシートを敷いたり、しっかりとした台の上に安置したりと、物理的な安全対策を心がけましょう。
湿気でカビないよう気をつけること
ご遺骨は湿気に弱く、放置するとカビが生えてしまうこともあります。骨壺の中に除湿剤を入れる、こまめに換気をする、押入れや床下など湿気の多い場所を避けるなど、適切な環境を整えることが重要です。
特に梅雨時期などは注意を払いましょう。
心配な場合は、専門業者に依頼し、粉骨した上で真空パックにしてもらうと安心です。
直射日光が当たらないようにする
ご遺骨や骨壺に直射日光が当たると、劣化や変色の原因になる場合があります。
特に装飾のある骨壺や写真、供花などを飾っている場合は、色褪せを防ぐためにも、日差しの強い場所は避け、カーテン越しのやわらかい光の入る場所がおすすめです。
将来的に誰が管理するのか決めておくこと
いずれご遺骨をどうするか、また誰が管理していくかを決めておくことも大切です。ご本人が元気なうちは良くても、将来的に介護施設に入る、家族構成が変わる、引っ越すなどの可能性も考えられます。
自分がいなくなったあとも、きちんと供養してほしいと思う場合は、その思いを託せるよう、家族で事前に共有し、記録に残しておくと安心です。
いったん納骨したご遺骨を家に置くには

現在納骨しているけれども、ご遺骨を自宅で供養したいという場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?その手順について説明します。
墓じまいをする
すでにお墓に納骨したご遺骨を自宅に戻したい場合は、墓じまいの手続きを行う必要があります。お墓を撤去して遺骨を別の場所へ移すことになりますので、自治体への申請と、現在お墓がある霊園や寺院の了承が必要です。
墓じまいの手続きには
- 改葬許可申請書
- 現在の埋葬証明書
- 新たな保管場所の受入証明書
などが求められます。ご遺骨を自宅に戻す場合も、この手続きが必要となります。
なお、自宅で供養する場合は、受入証明書は原則不要です。
ご遺骨を洗浄・乾燥させる
お墓に埋葬されていたご遺骨は、長年の湿気や土壌の影響で水分を含んでいることがあります。そのまま自宅に持ち帰るとカビや臭いの原因になる可能性があるため、持ち帰る前に洗浄・乾燥の処置を施すのが一般的です。
専門の石材店や葬儀社に依頼すれば、丁寧に対応してもらえます。清潔に保たれた状態であれば、家での保管や供養も安心して行えます。
ご遺骨を納骨する以外の供養の方法

納骨はしたくない(もしくはできない)、しかし自宅で供養するのも難しいという場合には、以下のような選択肢があります。
0葬
「0葬(ゼロそう)」とは、法要やお墓を持たず、ご遺骨の処分も業者に任せるという、供養の一切を簡素にした新しいスタイルです。
遺族が儀式にとらわれず、故人の希望や家族の事情に合わせて自由な形で送り出すことができます。生前に本人が希望していたり、家族との話し合いが十分にできている場合には、精神的・経済的な負担を軽減する選択肢となるでしょう。
散骨
ご遺骨を細かく粉骨し、海や山など自然の中に撒く散骨も、近年広がりを見せている供養方法です。自然に還るという考え方に共感する人が増え、宗教やお墓にこだわらないシンプルな供養として選ばれています。
ただし、散骨する場所や方法にはルールがあり、海洋散骨などを行う場合は専門業者に依頼するのが一般的です。自治体によっては規制があるため、事前確認が必要です。
樹木葬
自然の中で眠りたいという願いを叶えるのが樹木葬です。お墓の代わりに樹木を墓標とし、故人のご遺骨をその根元に埋葬します。
個人墓や共同墓など形式はさまざまですが、いずれも自然と共に生きるという理念に基づいており、特に宗教不問で申し込みができる霊園も多くあります。
費用面や管理のしやすさからも、近年注目されている供養スタイルのひとつです。
まとめ
ご遺骨を納骨せず、自宅に置いて供養するという選択は、決して特別なことではありません。法律的にも問題はなく、さまざまな供養の形が受け入れられる時代だからこそ、自分や家族にとって無理のない、納得のいく方法を選ぶことが大切です。
大切なのは「どうすべきか」よりも、残された人たちが「どうしたいか」ということです。
ただし、家に置く場合には保管環境や家族間の話し合い、将来的なことも視野に入れておく必要があります。また、0葬や散骨、樹木葬といった新しい供養の方法も選択肢のひとつです。
どの形であっても、故人を思い、心を込めて手を合わせる気持ちこそが、何よりの供養となるでしょう。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。