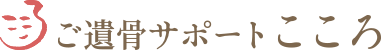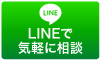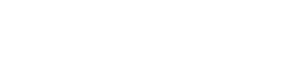ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
供養料の封筒で困らない!書き方・選び方・渡し方を徹底解説
お寺に供養料を渡す際のマナーがわからず、お困りではありませんか?普段、お寺との付き合いがない方にとっては、わからないことだらけで不安でしょう。
今回は、供養料の基本的な知識から、封筒の選び方、書き方、さらには渡す際のマナーまでを詳しく解説します。
事前にマナーを知っておけば、特別難しいことではありません。初めてでも自信を持ってお渡しできるようになります。
Contents
供養料とは供養してもらうためにかかる費用のこと
供養料とは、故人を弔うために僧侶に読経や供養をしてもらう際に支払う費用のことです。
供養料に含まれているもの
供養料に含まれる内容は、お寺や宗派、地域によって異なることがありますが、一般的には以下のようなものが含まれます。
ひとつは、供養そのものにかかる費用です。一般的に供養料といえば永代供養を指していることが多いので、そのための費用と理解しておけばよいでしょう。
供養にかかる読経料
今後、お寺でお経を読んでいただくことに対するお礼です。法要の種類(四十九日、一周忌、三回忌など)や、読経の長さ、参列者の人数などによって、金額が変動することがあります。通常は供養の時に「お布施」としてお渡ししますが、永代供養の場合はお寺にお任せするので、先に支払うのが一般的です。
お墓・納骨堂の使用料
お墓や納骨堂(屋内にあるお骨を納める施設)の永続的な使用料。霊園やお寺の規定によって、一定期間は個別に管理し、その後合祀される場合もあります。
お墓の管理・清掃費用
お墓や納骨堂の清掃、メンテナンスにかかる費用。個別墓で管理される場合は、お墓の維持費も含まれることがあります。
刻字料
故人の名前や戒名を墓石や納骨堂のプレートに刻む費用。別途費用がかかる場合もあるため、事前に確認が必要です。
その他の供養儀式の費用などが含まれます。
お寺の本堂や斎場の使用料
法要を執り行う場所として、お寺の本堂や斎場を使用した場合にかかる費用です。
祭壇の設営費
法要で使用する祭壇を設営するための費用です。祭壇の規模や装飾によって金額が変わります。
戒名料や位牌料は、供養料とは別に扱われるのが一般的です。
上記はあくまで一般的な解釈であり、供養料の名目で支払った金銭が、具体的にどの費用に充てられているのか、詳細な内訳がお寺や神社から明示されることは少ないです。
供養料は相続税の控除対象にならない
供養料は相続税の計算上、相続財産から控除されるものではありません。
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続や遺贈によって取得した際に課税される税金です。この相続財産の総額から、葬儀費用など一部の費用を控除することができますが、供養料は、「葬儀費用」には含まれません。
葬儀費用は、亡くなった方を弔い、埋葬するために直接的にかかった費用を指します。具体的には、通夜や告別式の費用、火葬・埋葬費用、霊柩車代などが該当します。
それに対して供養料は、納骨時や四十九日法要、一周忌法要など、葬儀後に行われる法要や儀式に対して支払われるものです。これらは、故人の冥福を祈り、追善供養を行うためのものであり、葬儀とは目的が異なるためです。
供養料とお布施の違い

供養料とお布施は、どちらも僧侶に対して渡す金銭ですが、それぞれの目的や意味が異なります。
簡単にいうと、お布施は「僧侶への感謝の気持ち」として渡すお金であり、供養料は「供養を行うための具体的な費用」として支払うものです。
お布施は読経へのお礼だから金額の決まりはない
お布施は、法要や葬儀などで僧侶に読経や供養をしていただいたことに対する、感謝の気持ちとしてお渡しする金銭です。お寺は、檀家の方々からのお布施によって維持運営されています。お布施は、お寺の活動を支える大切な資金源となります。
「布施」という言葉自体に「見返りを求めない施し」という意味合いがあり、本来はお寺や僧侶への経済的な援助、つまり寄付という性質を持つものです。そのため、「いくら払わなければならない」という明確な金額は存在しません。
お布施は、それぞれの経済状況に合わせて、包むものと考えられています。無理のない範囲で、感謝の気持ちを表すことが大切です。
供養料の他にお布施が必要なのか?
供養料とお布施は、法要の種類や地域、お寺の考え方によって、どちらか一方のみを渡す場合と、両方渡す場合があります。
法要の案内などで、お寺から「供養料」として金額が提示されている場合、その金額の中に読経料など、法要に必要な費用が全て含まれていることがあります。この場合は、基本的にお布施を別途用意する必要はありません。
供養料が、会場使用料や祭壇料など、法要の儀式そのものにかかる費用のみを指し、読経料が別途必要となる場合があります。この場合は、供養料とは別にお布施を包む必要があります。
永代供養の場合は、通常、法要の読経に対するお布施分も含まれていますので、供養料の内訳を見て判断すると良いでしょう。
迷ったら、事前に寺院や霊園に確認してみてください。「法要の際にお渡しするものは、供養料の他に何か必要でしょうか?」と直接尋ねることで、お寺の考え方や地域の習慣に合わせた準備ができます。
供養料は白無地の封筒に入れる
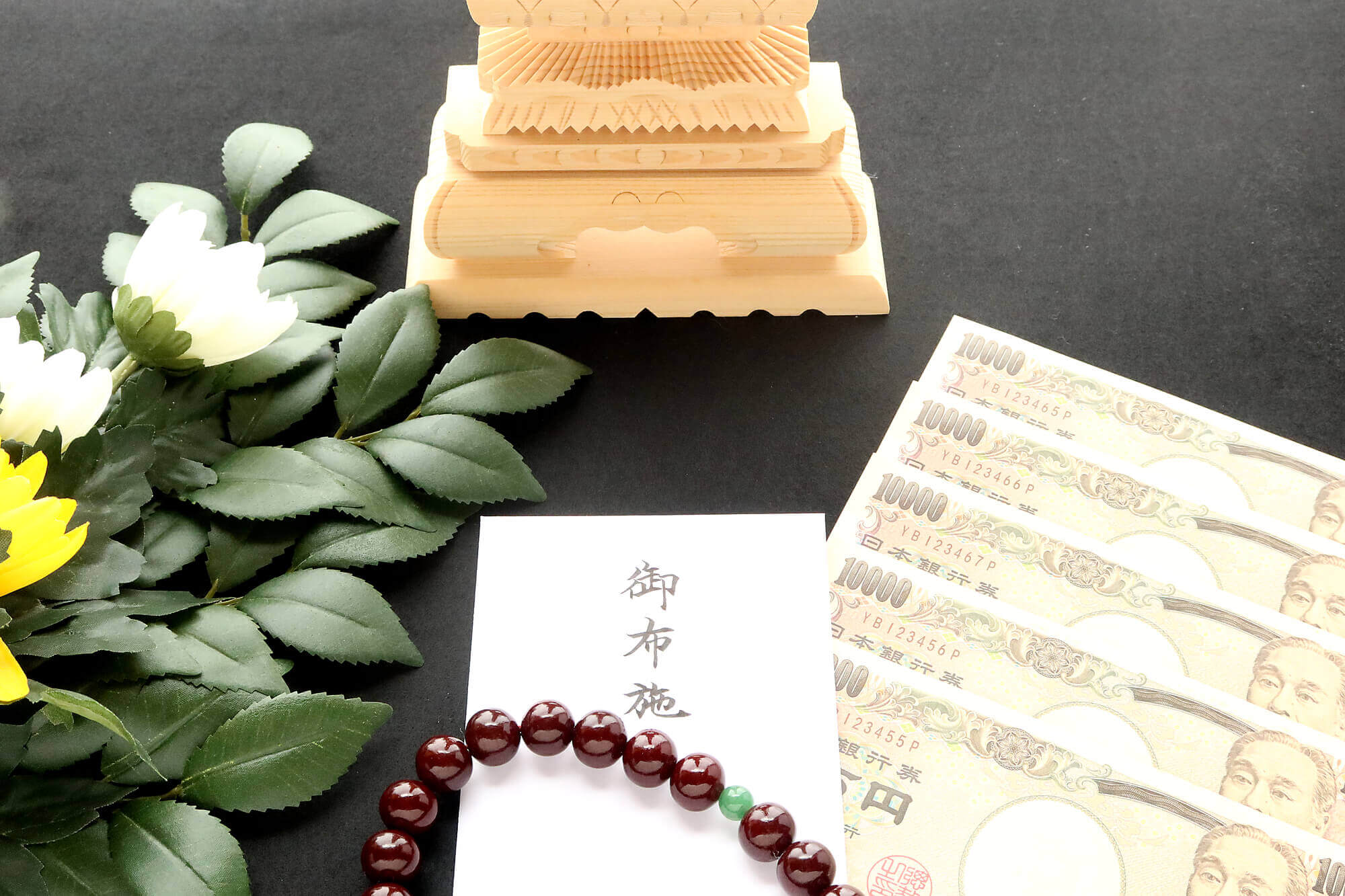
供養料を僧侶やお寺に渡す際は、白無地の封筒に入れるのが基本のマナーです。香典やお祝い事とは異なり、供養料は「感謝の気持ち」を伝えるものなので、シンプルで控えめな封筒を選ぶことが大切です。
適切な封筒の種類
供養料の封筒には、以下のような種類を選ぶのが一般的です。
- 白無地の封筒(シンプルで基本的なもの)
- 水引や装飾のないもの
- 郵便番号のないもの
お寺や宗派による違いが少なく、最も無難で、どの法要にも使用できます。
伝統的な方法として、奉書紙(厚手の和紙)に包んで渡すこともあります。
一般的な法要では白封筒で問題ないですが、格式を重んじる場合やお寺の方針に従う場合には、奉書紙が適しています。
サイズの選び方
封筒のサイズは、供養料の金額や入れる紙幣の枚数によって決めるとよいでしょう。
| 封筒のサイズ | 特徴・用途 |
| 長形4号(90×205mm) | 一般的な封筒サイズ。1~5万円程度の供養料に適している |
| 長形3号(120×235mm) | 少し大きめの封筒。5万円以上包む場合に向いている |
| 角形6号(162×229mm) | 奉書紙に包んだ上で入れる場合に適している |
紙幣を折らずに入れる場合は、「長形4号」や「長形3号」が適しています。紙幣は折らずに封筒に入れるのがマナーなので、適切なサイズを選ぶことが大切です。
供養料の封筒の購入場所
供養料用の封筒は、以下の場所で購入できます。
- 文房具店・100円ショップ
- 仏具店・お寺の売店
- インターネット通販(Amazon・楽天など)
100円ショップでは、仏事用の封筒も販売されていることが多いですし、「長形4号」「長形3号」など、一般的なサイズが揃っています。
供養料をお渡しするときの封筒の書き方など

供養料は、故人の霊を慰め、法要を営んでくださる僧侶や寺院への感謝の気持ちを込めてお渡しするものです。失礼のないように、封筒の書き方やお金の入れ方にもマナーがあります。
表書き
供養料の表書きには、以下のような言葉を使用します。
- 御供養料:ほとんどの宗派で使用できる、最も一般的な表書き
- 御回忌料:年忌法要(一周忌、三回忌など)に用いる
- 御法要料:法要全般に用いることができる
- 御経料:読経をしていただいた場合
迷ったら、「御供養料」で問題ありません。
浄土真宗の場合の表書き
浄土真宗では、故人は亡くなるとすぐに仏様になると考えられているため、故人への供養という概念がありません。
そのため、「供養」という表現は避け、「御布施」や「御礼」、もしくは「永代経懇志(えいたいきょうこんし)」と書くのが適切です。
裏書
封筒の裏面には、差出人の情報(住所と氏名)、そして包んだ金額を記載します。
- 住所と氏名:封筒の裏面左下に、縦書きで住所と氏名を記載する
- 金額:封筒の裏面中央に、縦書きで金額を記載する
氏名は、個人ならフルネーム、複数人なら連名で書きます(原則3名まで)。人数が多い場合は、代表者の名前だけ書き、「他○名」と補足します。
金額の書き方の注意
供養料の封筒に金額を記入する場合、正式な漢数字を使うのがマナーです。
漢数字で書く理由は、改ざんを防ぐためです。 普通の数字(1、2、3など)では、書き換えができてしまうので、あえて旧字体で書きます。
<金額の例>
- 一万円→金壱萬円
- 三万円→金参萬円
- 五万円→金伍萬円
「金」から書き始め、最後に「円」を付けましょう。
薄墨ではなく濃墨を使う
香典袋では薄墨を使うのが一般的ですが、供養料の封筒は濃墨で書きます。
供養料はお寺や僧侶への謝礼であり、弔事の場とは異なるため濃墨を使用します。
毛筆で丁寧に書くのがベストですが、黒の筆ペンでも大丈夫です。家に筆がないという人も多いと思いますが、コンビニでも筆ペンは売っていますので、当日お渡しするまでに準備はできるでしょう。
供養料のお金の入れ方
供養料を入れる際のお札の向きにもマナーがあります。
- お札の表側(肖像がある面)を封筒の表側に向ける
- 肖像が上になるように入れる
お札は折らずにそのまま入れてください。
新札を用意するとより丁寧
供養料を入れる際には、新札を用意するとより丁寧です。
香典では、事前に準備していた印象を与えないため旧札を使いますが、お布施や供養料は、僧侶やお寺への感謝の気持ちを表すものなので、新札が好まれます。
供養料を渡すときに注意すること

供養料を渡す際には、単に封筒を準備するだけでなく、正しい渡し方やマナーを意識することが大切です。
封筒をそのまま渡さない
供養料をお渡しする際に、封筒をむき出しのまま渡すのはマナー違反とされています。必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参するようにしましょう。
<渡し方>
- 袱紗を開いて、供養料の封筒を取り出す
- 封筒の向きを整えて、相手に正しく見えるようにする
- 両手で丁寧に渡す
袱紗ごと、渡さないようにしてください。袱紗はあくまで封筒を包むためのものなので、中身を出してから渡しましょう。
渡すタイミングは事前に確認しておくと安心
供養料を渡すタイミングは、法要の状況によって異なりますが、最も適切なタイミングは法要の前です。法要が始まる前に、僧侶へ挨拶をしながら渡します。
時間がなければ、法要後にお礼を伝えながら渡しても問題ありません。読経の後に、直接僧侶へ感謝を伝えながらお渡ししましょう。
ただし、法要後は僧侶がすぐに次の法要へ移る場合もあるため、迷ったら事前に渡すのが無難です。
最も確実なのは、事前に寺院に渡すタイミングについて確認しておくことです。「供養料は、いつお渡しすればよろしいでしょうか?」と尋ねてみましょう。
銀行振込ならそもそも手渡しの必要はない
最近では、お寺が供養料の銀行振込を受け付けている場合も増えてきています。事前に銀行振込が可能かどうかを確認すると、手渡しが不要になるケースもあります。
<振込の際のマナー>
- 振込先口座情報を確認する
- 振込名義:誰が振り込んだのかがわかるように、自分の氏名をフルネームで入力
- 振込手数料:原則として、振込手数料は依頼人側が負担
振込が完了したら、寺院に電話や手紙などで連絡を入れましょう。法要の日時、振込金額、振込名義などを伝えます。
法要当日は、振込をした旨を伝え、お礼を述べましょう。
供養料の相場

供養料の金額は、法要の種類・地域・お寺のしきたりによって異なりますが、おおよその目安があります。
<法要の種類による相場>
- 四十九日法要:3万円~5万円程度
- 一周忌法要:3万円~5万円程度
- 三回忌以降の法要:1万円~3万円程度
- 納骨法要:1万円~5万円程度
- お盆の法要(新盆・初盆以外):5千円~2万円程度
- お盆の法要(新盆・初盆):3万円~5万円程度
永代供養料としてお渡しする場合は、供養の期間やお墓の種類によって10万円~50万円以上、個別墓となると、それ以上になることもあります。
まとめ
供養料は、故人を偲び、法要を執り行ってくださる僧侶や寺院への感謝の気持ちを表すものです。適切な封筒を選び、表書きや裏書きのマナーを守ることは、相手への礼儀を示す上で非常に大切です。
表書きには「御供養料」や「御布施」と記入し、裏面には氏名と金額を書きます。お札は新札ではなく、軽く折り目のついたものを用意し、向きにも注意しましょう。
また、供養料を渡す際には、袱紗に包んで持参し、タイミングを見計らって丁寧に手渡すことが重要です。事前に寺院に確認することで、よりスムーズに、そして失礼なくお渡しすることができます。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。