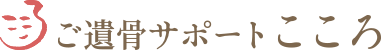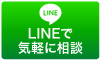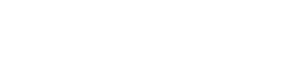ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
浄土真宗の納骨に必要なお布施の表書きや金額の相場について解説
浄土真宗では、どのようにお布施をお渡しすれば良いのか、金額の相場や封筒の書き方はどうすれば良いのかとお悩みの方へ、浄土真宗のお布施について詳しく解説します。
お布施の渡し方のマナーやタイミングについてもお話ししますので、迷っている方はぜひ参考にしてください。
Contents
浄土真宗のお布施の相場

浄土真宗の布施の金額の相場は、お葬式か法要かで金額が違ってきます。
葬儀の場合
浄土真宗のお布施の相場は、枕経からお通夜、葬儀までが10万円~30万円ほどです。
この相場の幅は、主に僧侶の人数の違いです。導師と副導師の2人、ときには3人以上になることもあり、人数が増えるほどお布施も多めにお渡しします。
お布施の内訳
- 枕経:1万円
- お通夜:2万円~3万円
- 導師:7万円~15万円
- 副導師:7万円~10万円
このほかに、御車代をお渡します。お布施は、枕経やお通夜のたびにお渡しするのではなく、葬儀が終わってからまとめてお渡ししますが、御車代についてはその都度お渡ししましょう。
最近ではお一人でお勤めを行う小規模なお葬式が増えていますので、少ないお布施で済む場合もあります。
浄土真宗のお布施は、他宗派と比べると比較的低いです。他宗派は戒名料を含めると50万円を超えることもありますが、浄土真宗には戒名がありません。
戒名の代わりに「法名」を授かりますが、戒名のようにランクがないですし、そもそも戒名料のようなものが不要です。
その分、浄土真宗のお布施は他宗派より安い傾向があります。
ただし、格式の高い法名や院号を希望する場合は、有料になることがあります。たとえば、法名の前に「○○院」と院号をつける際、本山に申請する場合は、永代経懇志として20万円以上必要となります。
定額はないが不安ならお寺に相談してみる
お布施は感謝の気持ちを表すものですから、決まった金額はありません。こちらの気持ちで決めて良いものです。
ただし、お寺によってはお布施の金額を決めているところもありますし、その地域の風習もあります。
不安な場合は、一度お寺に聞いてみると良いでしょう。
法事や法要の場合
四十九日や一周忌の法要は3万円~5万円ほどです。納骨の法要など様々な法事がありますが、おおむねこのくらいの金額が相場とされています。
ほかにも、このような法要があります。
- 建碑法要(お墓を建てる法要):2万円~3万円
- 入仏法要(新しく仏壇を購入した時の法要):1万円~2万円
納骨法要は、四十九日や一周忌にあわせて行われることが多いです。法要と納骨を一緒に行う場合、5万円~10万円程度が相場となります。
法要をお寺で行う場合、場所代が必要となることもありますので、事前にお寺に確認しておくと安心です。
その他お車代など
お布施とは別に、僧侶に御車代や御膳料をお渡しすることがあります。
お車代は5,000円~1万円程度が相場とされていますが、どこから来ていただくのか、場所によっても変わってくるでしょう。新幹線などを使う場合は実費も考慮して金額を決めます。
ただし、自分の車で僧侶を送迎する場合は、御車代は不要です。
御膳料は、会食に参加されない場合にお渡しします。おもてなしの料理の代わりにお渡しするものですので、5,000円~1万円程度が相場とされています。
浄土真宗のお布施の表書などお渡しするときの注意点

ここからは、お布施をお渡しする際の注意点について解説します。
お布施の表書き
お布施の表書には、「お布施(御布施)」と書きます。「お経料」や「回向料(えこうりょう)」は僧侶にお渡しする謝礼であり、浄土真宗では使用しませんのでご注意ください。
お布施とは、読経していただいたときに僧侶に渡すお礼ですが、読経に対する対価ではなく、お寺のご本尊にお供えするものです。阿弥陀如来の念仏の教えを説いてもらったことに対する感謝の気持ちとしてお渡しするのです。
回忌法要の際は、「三回忌法要 御布施」などと記載します。
水引から下の部分には「○○家」もしくは喪主の名前を書きます。ここはその地域の風習にもよりますので、通常どのように書いているか、親戚に確認すると良いでしょう。
金額は中袋の表面に記載します。お布施の金額は、漢数字ではなく大字(だいじ、旧字体のこと)を使います。
- 5,000円→金伍仟圓
- 1万円→金壱萬圓
- 3万円→金参萬圓
(例:壱 、弐、参 、肆 、伍 、陸、漆、捌 、玖、拾、、佰 、仟 、萬)
なお、僧侶に御車代や御膳代をお渡しすることもありますが、それは僧侶に対してお渡しするものですから、お布施とは別に用意します。
お布施の裏書き
裏書きは、中袋があるかどうかで変わってきます。
中袋がついていれば、中袋の裏面に住所、電話番号を書いておきます。
ついていなければ、封筒の裏面に住所と電話番号、その横に少し開けて金額を書きます。
薄墨は使わない
これは浄土真宗に限ったことではないのですが、お布施の表書き・裏書きは、通常の濃い墨で書きます。
薄墨は、お通夜や葬儀に持参する香典袋で使うもので、参列者が故人様を追悼し、悲しみの気持ちを表すためのものです。
お布施に使う必要はないので、通常の墨で大丈夫です。
お布施の包み方
まず、現金をそのまま封筒に入れず、奉書紙に包んで入れます。奉書紙とは白い和紙の一つで、かつては公文書に用いられる紙でもありました。普通の和紙よりも厚いのが特徴です。
包み方の手順

- 奉書紙の長辺を上にして横に置き、左側が上に来るようにして少し斜めにおきます。このとき、ざらざらしている面を上にします。
- 中央よりも少し右にお金を置きます。
- お札の長さに合わせて、上下の部分を折りたたみます。
- 奉書紙の左側をお札に合わせて、お札が隠れるように折ります。
- 右側からも左側を覆うようにして包み、余った分はそのまま左側に織り込みます。
ツルツルした方が表になるように、紙の裏表を間違えないようにしましょう。
もし奉書紙がない場合でも、封筒に直接現金を入れないようにしてください。半紙で包みます。奉書紙や半紙は文房具店で購入できます。
お札の向きは、肖像画が袋の入り口に近くなるように、表にして入れます。
お布施の水引
浄土真宗のお布施は、水引がなくても構いませんが、水引を使う場合は黒白か、銀色にしましょう。
結び方は「結び切り」か「あわじ結び」です。
お布施をお渡しするタイミング
葬儀の時は、葬儀会場で僧侶に挨拶をする時にお渡しするのが一般的です。
法要の場合も、儀式が始まる前にお渡ししておくのがスムーズです。
ただし、お葬式も法要も、準備に忙しくて事前にお渡しするタイミングを逸してしまうこともあります。その場合は、お葬式や法要が終わった後、一息ついたタイミングでお渡ししても問題ありません。
ただし、法要の後の会食がある場合は、会場までご案内する時間もありますので、会食後にお車代と一緒にお渡しした方が良いでしょう。
もし会食を辞退された場合は、お帰りになるタイミングでお膳代と一緒にお布施をお渡しします。
当日バタバタしないように、会食に参加されるかどうか予定を聞いておくことをおすすめします。
失礼のないお布施の渡し方
お布施を渡す時は、そのまま直接手渡ししないようにします。
お布施をお渡しするための「切手盆」に乗せてお渡しします。まず、切手盆にお布施を置き、僧侶が表書を読めるようにお盆の向きを変えてお渡ししましょう。
もしくは、袱紗(ふくさ)に包んでお渡しします。お渡しする時に袱紗からお布施を取り出し、袱紗の上にお布施をのせます。
僧侶から見て表書が読めるように向きを変え、お渡しします。
なお、切手盆はご祝儀や不祝儀をお渡しする際にも使えるものなので、もし持っていなければこの機会に用意しておいても良いでしょう。
お渡しする時は、「御本尊様にお供えください」と挨拶をしお渡しします。お布施は僧侶に対する読経料ではなく、ご本尊にお供えするものだからです。
ただ、僧侶に対して感謝の気持ちを伝えたいこともあると思います。その場合は、ご本尊への挨拶の後に、「本日はありがとうございました」とお伝えすれば良いでしょう。
お布施は感謝の気持ちを表すもの

浄土真宗では、仏事を「不幸なこと」としてとらえておらず、仏様のありがたい教えを聞かせていただく尊い機会と受け止めています。むしろ、仏様とのありがたいご縁をいただく慶事としてとらえています。
そのため、「不祝儀」の形にこだわる必要はなく、水引の色にも特に決まりはありません。元来は水引なし、無地の奉書紙が使われていたといわれていますので、他の宗派と同じような形にしなくても良いのです。
本来、お布施についての決まったマナーは存在せず、仏様にお供えするという気持ちがあれば良いものです。
本来は金額の決まりもない
金額についても、あくまでも気持ちなのですから、こうでなければいけないという決まりはないのです。
ただし、あまりに少なすぎるとお寺側の感情を害してしまうこともありえるため、今回ご紹介したように、世間でいわれている相場を参考にして、金額を決めると良いでしょう。
迷ったら、お寺に聞いても差し支えありません。
浄土真宗には永代供養という概念がない
浄土真宗では、人が亡くなるとすぐに成仏するという教えがあるため、基本的に供養は必要ありません。
ただし、納骨するタイミングは、四十九日、一周忌、三回忌など他の宗派とほぼ同じです。
永代供養の代わりに、本山納骨という方法があります。
浄土真宗本願寺派は、喉仏の骨とそれ以外のご遺骨に分け、喉仏の骨は大谷本廟に、それ以外の骨は家のお墓に納めます。
浄土真宗東本願寺派は、大谷祖廟に全てのご遺骨を納めることが可能です。
なお、浄土真宗本願寺派と浄土真宗東本願寺派と分かれてはいるものの、お布施についての違いはありません。
まとめ
今回は、浄土真宗でのお布施の相場や渡し方のマナーについてご紹介しました。
お葬式から納骨、年忌法要など、お布施をお渡しする機会は何度かありますが、浄土真宗におけるお布施は、僧侶への御礼ではなく、御本尊にお供えするものです。
相場は10万円~30万円ほどで、戒名料が必要ない分、他宗派よりも低めの傾向があります。
お渡しする時は封筒のまま手渡しするのではなく、切手盆にのせるか、袱紗に包んでお持ちします。
お布施は、感謝の気持ちが最も大切であるとはいえ、失礼のないよう、今回ご紹介した注意点に気をつけてお渡ししてみてください。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。