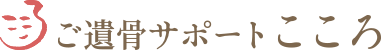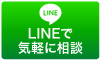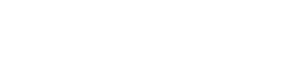ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
一周忌でお墓がない場合はどうすればいい?供養の方法5つ
一周忌は、故人を偲び、あらためて感謝や祈りを捧げる大切な節目であり、納骨のタイミングとして考えている方も多いでしょう。
しかし近年では「お墓をまだ建てていない」「お墓を持たない選択をした」など、さまざまな事情で一周忌に納骨ができないケースも増えています。
お墓がないままでも一周忌の供養はできるのか、納骨の時期は決まっているのか。
そんな不安や疑問を感じている方のために、この記事では一周忌にお墓がない場合の供養の方法や、納骨のタイミング、お墓を持たない場合の注意点などをわかりやすく解説します。
Contents
納骨の時期に決まりはある?法律と慣習の違い
ご遺骨をお墓に納める「納骨」は、多くの方にとって大切な節目のひとつです。しかし、納骨の時期について「いつまでに済ませなければならないのか」と悩む人も少なくありません。
いつまでに埋葬しなければならないという決まりはない
結論からいえば、納骨の時期について法的な決まりはありません。日本の法律上、ご遺骨をすぐにお墓に納めなければならないという規定はなく、しばらく自宅で保管していても問題はないのです。
実際、経済的な事情やお墓の準備が整っていない場合、数ヶ月から数年にわたり、自宅でご遺骨を安置しているケースも珍しくありません。
宗教や地域による違いに注意
ただし、宗教的な教えや地域の慣習によっては、納骨のタイミングに目安が設けられていることもあります。
たとえば仏教では、四十九日法要にあわせて納骨を行うのが一般的とされる宗派もありますし、一周忌や三回忌などの年忌法要に合わせて納骨することもあります。
また、地域によっては「先祖代々の墓に入れるのは○回忌のあと」というような独自のしきたりが存在することもあるため、親族や菩提寺に確認しておくと安心です。
現代ではライフスタイルや価値観の多様化により、納骨のタイミングもより柔軟に考えられるようになってきました。
- 法的には自由
- 宗教的には目安がある
- 地域では風習がある
という三つの視点を踏まえ、故人やご遺族の思いを大切にしながら判断することが大切です。
5つの供養方法

一周忌を迎える時点でまだお墓が完成していない、あるいは建てる予定がないというケースは、近年では決して珍しいことではありません。
お墓がなくても、故人を偲び、心を込めた供養を行うことは十分に可能です。ここでは、一周忌にお墓がない場合でもできる供養の方法を5つご紹介します。
1.お墓を建てるまで自宅に置いておく
お墓の建立には時間と費用がかかるため、一周忌の時点でまだ完成していないということもあります。その場合、ご遺骨を一時的に自宅に安置しておくのは、法的にも問題ありません。
仏壇の近くや専用の骨壺台を用意し、お花やお線香を供えて日々手を合わせることで、丁寧な供養ができます。
ただし、湿度管理などの保管環境には注意が必要です。ご遺骨にカビが生えるのを防ぐためにも、風通しの良い場所を選び、直射日光が当たらないように気をつけてください。
2.永代供養墓で合祀する
将来的にお墓を持つ予定がない、または子や孫に墓守りの負担をかけたくないという方に選ばれているのが、永代供養墓での合祀です。合祀とは、他の方の遺骨と一緒に埋葬される方法で、寺院や霊園が永続的に管理・供養をしてくれます。
個別安置型と合祀型があり、初めは個別に安置し、一定期間後に合祀されるプランもあります。一周忌に合わせて納骨式を行い、その後の供養もお寺に任せることで、安心感を得られるという声も多く聞かれます。
3.手元供養にする
最近注目されているのが、ご遺骨の一部を自宅で手元に置いて供養する「手元供養」という方法です。
小さな骨壺やペンダント、インテリア調の供養具など、現代の暮らしに溶け込むスタイルも豊富に揃っており、場所を取らずに心の拠り所として日常に寄り添うことができます。
手元供養には、ご遺族が故人を身近に感じながら過ごせるというメリットがあります。すべてのご遺骨を手元供養することもあれば、一部だけを取り分けて行うケースもあります。
4.散骨する
自然の中に遺骨を還す散骨も、お墓を持たない供養のひとつとして広まりつつあります。海や山など、故人が好きだった場所に遺骨を撒くことで、自然に還るという考え方に共感する人も増えています。
散骨は、法律で禁止されているわけではありませんが、自治体の条例によって、散骨場所が制限されていることがあります。
また、ご遺骨を撒くという行為は非常にデリケートな問題ですから、周囲への配慮が必要です。専門の業者に依頼するのが一般的で、費用や手続きについても事前に確認しておくと安心です。
5.樹木葬にする
墓石の代わりに樹木を墓標とする「樹木葬」も、近年人気を集めている供養方法のひとつです。自然志向のライフスタイルに合った選択肢として注目されており、従来のお墓のイメージにとらわれない点が魅力です。
樹木葬には個別区画型と合祀型があり、事前に契約すれば、一周忌に合わせて納骨も可能です。霊園や寺院によっては、一周忌法要とセットになったプランもあるため、早めに相談しておくとスムーズに進められるでしょう。
お墓を持たない選択が増加中|法律や宗教上の問題は?

少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、「お墓を持たない」という選択をする人が増えています。特に都市部では、お墓の継承者がいない、費用面の負担が大きい、供養の形を自分らしく選びたいといった理由から、従来の「お墓ありき」の価値観を見直す動きが広がっています。
しかし、いざ自分たちがその選択をしようとすると、「法律的に問題はないの?」「宗教的に大丈夫なの?」といった疑問や不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
ここでは、お墓を持たないことに関する法律面・宗教面の考え方、そして注意すべきポイントを解説します
お墓に埋葬しなくても法律上は問題ない
日本の法律では、ご遺骨は「墓地、埋葬等に関する法律」により、自治体の認可を受けた場所でなければ埋葬できないと定められています。しかしこれは「勝手にどこかに埋めてはいけない」という意味であり、お墓を持っていないこと自体が違法になるわけではありません。
つまり、納骨堂や永代供養墓、散骨、手元供養といった選択肢もすべて、適切な形で行えば法律上の問題はありません。自宅でご遺骨を一定期間保管しておくことも、もちろん法律には触れませんので安心してください。
ただし、将来的に他人に譲ることができない(相続できない)供養方法を選ぶ場合は、慎重に考えておく必要があります。ご家族やご親族とよく話し合ったうえで、方針を決めていきましょう。
成仏できないなど宗教上の問題もない
「お墓に入れなければ成仏できないのではないか」という声を耳にすることもありますが、宗教上も必ずしもお墓が必要というわけではありません。たとえば仏教では、供養の本質は「亡くなった方を想い、祈りを捧げること」にあります。
寺院によって考え方に多少の違いはあるものの、多くの宗派では手元供養や永代供養といった形でも「正しい供養」として認められています。また、納骨のタイミングも厳密に定められているわけではなく、一周忌や三回忌に合わせて行うのも一般的な選択肢のひとつです。
重要なのは、「こうしなければならない」という形式にとらわれすぎず、故人と遺族の気持ちを大切にすることです。その想いが供養となり、故人の魂を慰めることにつながります。
いずれはなんらかの対処が必要となる
お墓を持たないという選択は、経済的・心理的な負担を軽くする一方で、いずれ、遺骨をどこに安置するか、誰が管理するかといった問題は必ず発生します。
たとえば手元供養をしていた場合でも、遺族が高齢になったり、引っ越しをしたりすれば、「その後どうするか」を誰かが判断する必要があります。同様に、合祀や散骨を希望していたとしても、実行するタイミングや費用、手続きの問題が生じることもあります。
そのため、お墓を持たないと決めた場合でも、「最終的にどこに納骨・埋葬するのか」という着地点をある程度イメージしておくことが大切です。生前に信頼できる家族や行政書士と話をしておく、遺言書を残しておくといった備えがあると、残された人も安心して対応できます。
一般的な納骨のタイミング

納骨のタイミングには、「いつまでにしなければならない」という厳密なルールはありませんが、日本では一定の慣習や節目に合わせて納骨することが一般的です。ここでは、代表的なタイミングと、それぞれの背景についてご紹介します。
四十九日
最も多くの方が納骨を選ぶタイミングが、「四十九日(しじゅうくにち)」の法要です。仏教においては、亡くなってから49日間は魂が現世とあの世の間をさまようとされており、この期間の最後に極楽浄土へ旅立つと考えられています。
そのため、四十九日の法要は故人の旅立ちを見送る重要な節目とされ、納骨を同日に行う家庭が多いのです。
また、四十九日までは「中陰」と呼ばれる期間にあたり、白木位牌や仮の遺影を使うなど、葬儀後の生活においても特別な意味を持っています。
一周忌や三回忌
事情があって四十九日に納骨できなかった場合、次の大きな節目として選ばれるのが「一周忌」や「三回忌」です。これらは年忌法要と呼ばれ、親族が集まる機会にもなりやすいため、法要と納骨を一緒に行うことにより、スムーズで負担の少ない形にできるというメリットがあります。
一周忌は故人が亡くなってからちょうど1年目に行う法要であり、仏教の教えでは故人の霊が家庭に戻ってくる「最初の年忌」として大切にされます。三回忌も同様に、節目のタイミングとして選ばれやすいです。
タイミングを逃してしまったらどうすればいい?
さまざまな事情により、四十九日や一周忌のタイミングで納骨ができなかったとしても、焦る必要はまったくありません。日本の法律では納骨の期限は定められておらず、遺骨を自宅で保管することも認められています。
実際に、
- お墓が未完成だった
- 気持ちの整理がつかなかった
- 家族間で意見がまとまらなかった
など、納骨を延期する理由は人それぞれです。
大切なのは、ご家族が納得し、無理のないタイミングで納骨できること。どうしても節目に合わせたい場合は、一周忌を過ぎてから、次の年季法要のときに納骨することも可能です。
また、寺院や霊園に相談すれば、個別に納骨式を行うこともできます。
お墓がないことで起きる3つの問題と注意点

お墓を持たないことは、経済的・精神的な負担を軽減する一方で、具体的なトラブルや悩みにつながる可能性もあります。実際に供養を続けていく中で、「思わぬ困りごとが出てきた」と感じる方も少なくありません。
ここでは、お墓がないことによって起こりやすい問題や注意点を3つに分けて解説します。
ご遺骨を埋葬する場所がない
お墓がない場合、最も大きな問題は「遺骨を最終的にどこに安置するかが決まっていない」ということです。自宅に置いておくことは一時的には可能ですが、長期間そのままにしておくと、将来的に誰が管理するのか、どのように引き継ぐのかといった問題が発生します。
特に高齢のご遺族が手元供養をしている場合、ご本人が亡くなった後の遺骨の扱いが不透明になるケースもあるため、注意が必要です。また、納骨堂や樹木葬など自宅以外で供養する際にも、事前に契約内容や管理体制をよく確認しておくことが大切です。
お参りする場所がない
お墓は、遺族が故人を偲び、手を合わせる「場」としての役割も果たしています。お墓がないということは、家族や親族が節目のたびに集まり、お参りする場所がないということでもあります。
とくに、遠方に住んでいる親族や孫世代にとっては、供養の気持ちがあっても「どこに行けばいいのか分からない」「手を合わせる場所がない」と感じてしまうことも。結果として、供養の習慣そのものが薄れてしまう可能性もあります。
そのため、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などのお参りできる代替手段を設けておくことは、残された家族への配慮としても有効です。
適切に保管しないとご遺骨にカビが生えたりする
ご遺骨を自宅に長期間安置する場合、保管環境には十分な注意が必要です。特に日本の高温多湿な気候では、骨壺の中に湿気がこもることでカビが発生することがあります。
カビが生えると、ご遺骨の損傷だけでなく、精神的なショックも大きいもの。こうした事態を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 骨壺を乾燥剤と一緒に保管する
- 風通しの良い場所に安置する
- 定期的に点検する
- 密閉型の納骨箱や手元供養用の専用ケースを使用する
「まだお墓を決めていないからとりあえず置いておく」という感覚ではなく、丁寧に、敬意をもって管理する姿勢が大切です。
供養の方法で迷ったら|選び方と家族の話し合い方

お墓を建てるかどうか、納骨のタイミングをどうするか、永代供養にするか散骨にするか。
故人を偲ぶ供養の方法にはさまざまな選択肢があるからこそ、迷いや不安がつきものです。「この選択で本当に良かったのだろうか」と、あとから悩む人も少なくありません。
そんなときに大切なのは、ひとりで抱え込まず、家族や親族としっかり話し合うことが大切です。そして、現実的な観点からも、費用や管理のしやすさなどを比較検討することが、後悔しない供養につながります。
家族、親族とよく話し合う
供養の方法は、単なる形式ではなく、故人への想いや、残された家族の心の整理に深く関わる大切な行為です。そのため、できるだけ多くの家族や親族と意見を交わし、「それぞれがどんな思いを持っているのか」「どんな形なら皆が納得できるのか」を確認することが重要です。
とくに、お墓を持たない選択をする場合は、将来の継承や管理のことまで視野に入れておく必要があります。たとえば次のような話し合いが有効です。
- 納骨先をどうするか(自宅/納骨堂/散骨など)
- 宗教的・感情的なこだわりがあるか
- 誰が管理・供養を担うのか
- 遠方の親族の参加や意向はどうか
「みんなで納得して決めた」という実感が、供養のあり方をより深いものにします。
供養の方法を費用で比較してみる
どんなに想いがこもっていても、現実には費用面も無視できません。供養方法によってかかる費用や継続的な負担は大きく異なります。たとえば以下のような違いがあります。
| 供養方法 | 初期費用の目安 | 維持費 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般墓(お墓) | 100万円~300万円前後 | 年1万円程度 | 伝統的で家族代々受け継げる |
| 永代供養墓 | 30万円~80万円程度 | 基本なし(最初に支払い済み) | 継承不要で寺院に任せられる |
| 納骨堂 | 20万円~70万円程度 | 年間管理費あり | 室内型でアクセスしやすい |
| 散骨 | 5万円~20万円程度 | なし | 自然志向・供養の形は残らない |
| 手元供養 | 1万円~10万円程度 | なし | 家の中で日々供養できる |
このように、それぞれの供養方法にはメリット・デメリットがあり、費用感も大きく異なります。
無理をして高額な方法を選ぶよりも、現実的な予算のなかで故人を偲ぶ気持ちを大切にする方が、心のこもった供養になるはずです。
納骨式の流れと準備リスト|一周忌と合わせて行う場合も

納骨式とは、ご遺骨をお墓や納骨堂などに正式に納める儀式のことを指します。仏教をはじめとした宗教儀礼の一環として行われることが多く、一周忌や三回忌といった年忌法要と同時に実施されることも一般的です。
一周忌の節目に納骨を予定している方は、事前にしっかり準備を整えておくことが大切です。ここでは、納骨式までの流れと具体的な準備リストを時系列でご紹介します。
納骨式の日にちを決めてお寺に連絡する
まずは、納骨式を行う日程を決めることが第一歩です。多くの場合、一周忌の法要と同じ日に設定されますが、寺院や霊園の都合、参列者の予定などを考慮しながら、可能であれば1~2ヶ月前には決定しておくと安心です。
日程が決まったら、菩提寺や霊園に納骨式をお願いする旨を連絡しましょう。菩提寺がある場合は、その宗派の作法に従って進められますし、霊園や納骨堂の場合でも、法要を一緒に執り行ってくれるケースが多くあります。
親戚や知人に連絡をする
日程と会場が決まったら、親戚や故人に縁のあった方々へ案内の連絡を入れます。特に高齢の方や遠方の親族がいる場合は、早めに連絡しておくとスケジュールを調整しやすくなります。
案内状を郵送することもありますが、近年は電話やLINE、メールで連絡する家庭も増えてきました。連絡の際には以下のポイントを伝えておくとスムーズです。
- 納骨式と法要の日程・時間・場所
- 集合場所や駐車場の有無
- 会食の有無や
- 服装の注意点
人数が確定したら会食や引き出物の準備をする
出席者のおおよその人数が把握できたら、会食(お斎)や引き出物の手配に進みます。法要後の会食は、故人を偲びながら親族や知人と語り合う大切な場でもあり、近年では仕出し料理や法要会館の利用も一般的になっています。
また、引き出物(返礼品)は地域の慣習にもよりますが、タオルやお菓子、カタログギフトなどが選ばれることが多いです。予算や人数に応じて無理のない範囲で準備を進めましょう。
お供物を用意する
納骨式では、お供物(おそなえもの)として果物や菓子、故人が好きだった品などを仏前に供えるのが一般的です。地域や宗派によって差はありますが、見た目のバランスや彩りも意識すると、祭壇がより温かい雰囲気になります。
お供物は、お寺に持ち込めるかどうか事前に確認し、複数の家庭で持ち寄る場合は内容が重ならないよう配慮しましょう。法要後に参列者へ分けて持ち帰ってもらう「お下がり」としても活用できます。
納骨式の後、会食へ
納骨式が無事に終わったあとは、参列者とともに会食の場へ移動します。ここでは、故人の思い出話に花を咲かせたり、日頃なかなか会えない親族同士の交流が生まれたりと、和やかな時間が流れることも多いです。
会食の締めくくりには、喪主や代表者から感謝のあいさつを述べ、参列のお礼と今後の支援への感謝を伝えると、丁寧で温かな締めくくりとなります。
まとめ
一周忌という大切な節目に「まだお墓がない」「納骨のタイミングを逃してしまった」と悩む方は、決して少なくありません。ですが、納骨や供養のあり方に明確な“正解”はなく、ご家族の想いと状況に合わせた方法を選ぶことがもっとも大切です。
法律上、納骨の期限は定められておらず、近年ではお墓を持たない選択肢も広がっています。手元供養や永代供養、散骨や樹木葬といった多様な供養方法がある中で、ご家族の希望や将来の管理面、費用などを含めて丁寧に話し合うことが、後悔のない供養につながります。
もしお墓埋葬できる場合は、一周忌に合わせて納骨式を行うことで、気持ちの区切りにもなり、故人との絆をあらためて感じる機会となるでしょう。いずれにせよ、どの方法を選んだとしても、故人を想う心がもっとも大切な供養のかたちであることに変わりはありません。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。