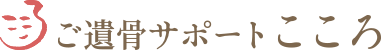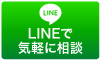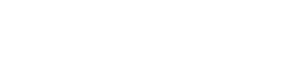ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
法事と法要との違いとは?意味・種類・流れ・マナーまでやさしく解説
「法事って、そもそも何のためにやるの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
法事とは、亡くなった方の冥福を祈り、節目ごとに供養を行う、大切な仏教行事です。
しかし初めての法事を営む時は、「法要との違いがわからない」「何回忌までやればいいの?」「マナーや服装が不安」など、戸惑うことも多いものです。
そこで今回では、法事の意味や目的をはじめ、法要との違い・種類・当日の流れ・マナーまで、わかりやすく解説します。
初めて喪主を務める方や、親族として参加する方も、ぜひ参考にしてください。
Contents
法事とは?意味と目的を知ろう
法事を行う意味と目的について、解説します。
そもそも法事とは何か
法事とは、仏教における故人の供養を目的とした、行事の総称です。
一般的には、僧侶による読経を中心に、焼香やお墓参り、会食などの一連の流れを含めて「法事」とされています。
身内や親族が集まり、故人を偲ぶとともに、感謝の気持ちを伝える場でもあります。
供養の一環としての法事の意味
仏教の教えでは、亡くなった人の魂は一定期間さまよい、その後、浄土へと旅立つとされています。
そのため、決まった日程で供養することで、故人の魂が安らかに成仏できるように祈るのが法事の目的です。
また、法事は単なる宗教的な行事ではなく、残された家族や親族の心の整理の機会としても、大切な意味を持っています。
つまり法事は、日常の中で故人のことを改めて思い出し、気持ちを整える時間でもあるのです。
家族や親族が集まる意義
現代では核家族化が進み、それぞれの家庭が忙しく、家族や親戚が集まる機会が減ってきています。
そのような中で、法事は親族同士が顔を合わせ、つながりを再確認する貴重な機会となるでしょう。
故人を中心に、世代を超えて語らい、絆を深める場となることも少なくありません。親戚同士の付き合いなど面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、親族同士だからこそ、故人の思い出を共有できることもあるはずです。
法事と法要の違いは?

ここで、法事と法要の違いについても説明します。
法要は「読経」、法事は「一連の流れ」
「法事」と「法要」は、似たような言葉ではありますがが、実は少し意味が異なります。
法要とは、僧侶による読経や儀式そのものを指す言葉で、仏教の教えに基づいた正式な供養行為のことです。
一方で、法事はその法要を含めた全体の流れを意味します。
読経だけでなく、参列者の焼香、会食、引き出物の手配など、故人を偲ぶための一連の行事全体を「法事」と呼ぶのです。
セットで使われることも多い
実際の場面では、「〇〇回忌の法事をする」「法要に参列する」など、両者をあまり区別せず使われることも珍しくありません。
ですが本来は、
- 法要:宗教的な儀式そのもの(読経・焼香など)
- 法事:その法要を含めた行事全体(会食など含む)
という違いがあることを覚えておくと、より丁寧に使い分けることができます。
法事の種類とスケジュール
法事には、大きく分けて「忌日(きにち・きじつ)法要」と「年忌法要(ねんきほうよう)」の2種類があります。
忌日法要は、故人が亡くなってから日数ごとに行われるもので、主に初年度に集中しています。一方の年忌法要は、命日から1年、3年と年単位で行うものです。
それぞれに意味や目的があり、宗派や地域によっても慣習が異なることがあります。
忌日法要(亡くなった年に行う法事)の種類
故人が亡くなった日を起点に、決められた日数ごとに供養を行うのが忌日法要です。主に、このような種類があります。
- 初七日(しょなのか)/7日目
- 二七日(ふたなのか)/14日目
- 三七日(みなのか)/21日目
- 五七日(いつなのか)/35日目
- 六七日(むなのか)/42日目
- 七七日(なななのか)/49日目(満中陰)
- 百カ日(ひゃっかにち)/100日目(卒哭忌)
僧侶を招いての読経や焼香を行い、家族や親族が集まって故人を偲びます。
初七日(しょなのか)とは
初七日とは、故人が亡くなった日を含めて7日目に行う法要のことです。
仏教では、人は亡くなってから7日ごとに「閻魔(えんま)さま」の裁きを受けるとされており、その最初の審判日がこの初七日とされています。
本来であれば、亡くなった日から数えて7日目に改めて僧侶を招いて法要を営むものですが、最近では火葬当日や葬儀と合わせて行う「繰り上げ初七日」が一般的です。
遠方から参列する親族の負担を減らすという配慮から、葬儀と同日に行うケースが増えています。
ただし、地域や宗派によっては本来の7日目に別途執り行う場合もありますので、お寺と相談して決めるのが安心です。
四十九日(しじゅうくにち)・七七日(しちしちにち)とは
四十九日(七七日)とは、故人が亡くなってから49日目に行う最も重要な忌日法要です。
仏教では、この49日間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、故人の魂が極楽浄土へ旅立つまでの期間とされています。
そのため、四十九日をもって喪に服す期間の「満中陰(まんちゅういん)」が終わり、忌明け(きあけ)となる節目でもあります。
この日には、僧侶による読経のあとに納骨を行ったり、親族で会食を開いたりするのが一般的です。
香典返しや引き出物をこのタイミングで贈ることも多く、準備や段取りがやや多い法要となります。
故人を偲ぶと同時に、遺族の心の整理と、社会復帰への第一歩となる大切な日です。
百カ日(ひゃっかにち)・卒哭忌(そっこくき)とは
百カ日法要は、亡くなってからちょうど100日目に行う供養で、「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれます。
「卒哭」とは「泣くのを終える」という意味があり、この法要を境に深い悲しみから少しずつ日常へと戻っていく、気持ちの区切りとなる節目とされています。
必ず行う必要はないとされる法要ではありますが、地域によっては重んじられ、納骨式や仏壇の拝見などと合わせて営まれることもあります。
特に、四十九日に納骨できなかった場合に、百カ日で改めて納骨するケースも見られます。
その他の供養行事
その他、納骨などに合わせて、以下の法要があります。
開眼供養(かいげんくよう)
仏壇や墓石など、新しく仏具を設置した際に行う供養。魂入れの儀式ともいわれます。
納骨式
火葬後、遺骨をお墓や納骨堂に納める際の儀式。忌日法要と一緒に行うこともあります。
新盆(初盆)
亡くなってから初めて迎えるお盆のこと。親族や近しい人を招いて、手厚く供養を行います。
年忌法要(命日から年単位で行う法事)

年忌法要は、命日から一定年数ごとに行う法要です。
主な節目は以下の通りですが、地域や宗派によって多少前後することもあります。
- 一周忌(いっしゅうき)/1年後
- 三回忌(さんかいき)/2年後(※数え年で行うため)
- 七回忌/6年後
- 十三回忌/12年後
- 十七回忌/16年後
- 三十三回忌/32年後(弔い上げとされることも)
法事は年数が経つにつれて簡略化される傾向もありますが、もしその年に法要を営まなかったとしても、節目の年に故人を想う、その気持ちが何より大切です。
一周忌・三回忌はどう行う?
年忌法要の中でも、一周忌と三回忌は特に重視される節目の法要です。
この2つは親族が集まって行うことが多く、準備やマナーも意識しておきたいところ。それぞれの意味や流れを見ていきましょう。
一周忌の流れと注意点
一周忌(いっしゅうき)は、故人が亡くなってからちょうど1年目の命日に行う法要です。初めての年忌法要であり、忌明け後、最も丁寧に行われることが多い法要です。
僧侶を招いて読経を行い、焼香、お墓参りをした後、親族や親しい人たちで会食を設けるのが一般的です。
香典返しを用意したり、引き出物を準備したりと、葬儀や四十九日法要に近い段取りとなることもあります。
日程は必ずしも命日ぴったりでなくてもよく、命日前の週末に行うなど、親族が集まりやすい日を選んでかまいません。
また、日程を決める際は、お寺や僧侶の予定を早めに確認するようにしましょう。
三回忌の法要の考え方
三回忌(さんかいき)は、数え年で行うため実際には亡くなってから2年目にあたります。一周忌に次いで重要な年忌法要とされ、家族や近しい親族が集まって供養を行います。
一周忌ほど形式ばらずに行われることが多く、自宅での読経のみ、会食は省略するなど、やや簡略化される傾向にあります。
ただし、故人との関係性や家族の意向によって、しっかりとした形式で行うこともありますので、どのくらいの規模で行うか、親族とよく相談しましょう。
最近では、三回忌をもって区切りとするご家庭も多く、それ以降の法事は省略する場合も少なくありません。
とはいえ、最も大切なのは、気持ちを込めて供養することです。無理のない範囲で、故人を偲ぶ時間を大切にしましょう。
法事の準備と段取り
法事は、日程調整から会場の手配、参列者への案内まで、思っている以上にやることが多い行事です。
特に喪主や遺族が主催する場合は、早めの計画と、段取りよく準備を進めることが大切です。
以下に、一般的な準備の流れをまとめました。
1.日程を決める(お寺と相談)
まずは日程の決定が第一歩です。命日が平日にあたる場合は、土日にずらすケースも多いです。柔軟に考えましょう。
ただし、僧侶を呼んで読経をお願いする場合は、お寺の予定を最優先に調整した方が良いです。
日程が決まったら、会場や参列者にも早めに知らせます。
2.会場の選定と手配
法事を行う場所は、以下のような選択肢があります。
- 自宅
- 菩提寺(お寺)
- 会館(法要専用ホール)
- 霊園内の法要施設
- 飲食店の法事プラン付き個室
など。
僧侶の移動手段や駐車場の有無も考慮して、なるべくアクセスの良い会場を選びましょう。
また、法要後に会食を行う場合は、移動がスムーズな場所で一括手配できると安心です。
3.参列者に案内状を送り、出欠を確認する
日程と会場が決まったら、親族や参列者に案内状を送ります。
最近では、電話やLINEで済ませるケースも増えていますが、丁寧な対応をしたい場合は、封書やはがきでのご案内もおすすめです。
あわせて、
- 食事の有無
- 香典辞退の有無
などを明記し、返信期限を設けるとスムーズに準備が進みます。
4.会食・引き出物の準備
法要後の会食(お斎=おとき)を予定している場合は、料理の内容やアレルギー対応、席次の準備も大切です。
また、法事の際には、参列者への引き出物(香典返し)を用意するのが一般的です。
目安としては香典の半額~3分の1程度の品物で、日用品やお菓子などがよく選ばれます。
配送対応をしてくれる業者もあるため、参加できなかった方にも贈れるよう準備しておくと丁寧な印象になります。
法事当日の流れ

法事当日は、事前の準備が整っていれば、意外とスムーズに進みます。
とはいえ、慣れない方にとっては「どんな順番で進むの?」「何をすればいいの?」と不安も多いものです。
ここでは、一般的な法事当日の流れをご紹介します。
1.受付・会場到着
まずは受付を設けて、出欠確認や香典の受け取りを行います。受付係がいない場合は、喪主や家族が対応することもあります。
香典を受け取ったら、お礼の言葉と引き出物をお渡しするのが、基本的なマナーです。
2.法要(読経・焼香)
時間になったら、僧侶による読経(法要)が始まります。僧侶が故人の供養を行い、参列者が順番に焼香を行います。
このとき、以下のような流れで進むことが一般的です。
- 僧侶の入場・読経開始
- 喪主・親族から順に焼香
- 読経終了・僧侶による法話(ある場合)
読経中の私語やスマホの操作は控え、厳かな雰囲気を保ちましょう。
3.お墓参り(納骨を伴う場合も)
法要のあとにお墓参りを行うケースもあります。
とくに、四十九日法要や一周忌では、墓前で線香を手向け、改めて故人を偲ぶ時間を取ります。
また、納骨がまだの場合は、このタイミングで納骨式を行うこともあります。
4.会食(お斎・おとき)
法要・墓参りの後は、参列者で会食の場を設けるのが一般的です。
この会食を「お斎(おとき)」と呼び、故人をしのびながら親族同士の交流を深める機会となります。
会食の最後には、喪主が挨拶を行い、参列のお礼と今後のお願いを述べて締めくくります。
5.解散
会食終了後、引き出物を渡してお見送りをします。
お車代を用意する場合は、僧侶や遠方からの参列者に忘れずにお渡ししましょう。
法事のマナー

法事は故人を供養する大切な行事であると同時に、参列者同士が気持ちよく過ごす場でもあります。
基本的なマナーを押さえておくことで、主催側も参加側も安心して法事に臨むことができます。
法事に適した服装(男性・女性・子ども別)
法事の服装は、一周忌まではフォーマルを基本に、それ以降は略式でも可とされています。
ただし、地域の慣習や家族間の方針にもよるため、迷ったら主催者に確認するのがベストです。
男性の服装
一周忌まで(正式喪服)
- 黒無地のスーツ(光沢のないもの)
- 白のワイシャツ
- 黒無地のネクタイ
- 黒の靴・黒の靴下
- ベルト・時計などもできるだけ黒や地味な色を選ぶ
三回忌以降(略式喪服/地味な平服)
- ダークグレーや濃紺のスーツでも可
- ネクタイは黒で統一感を保つのが無難
女性の服装
一周忌まで(正式喪服)
- 黒のワンピース、アンサンブル、またはスーツ
- 肌の露出を避け、ストッキングは黒で統一
- 靴・バッグも黒で、装飾の少ないシンプルなもの
- アクセサリーは基本NG(許されるのは一連の白パールのみ)
三回忌以降(略式喪服/地味な平服)
- グレーやネイビーの控えめな服装も可
- スカート丈は膝下を意識、派手な色柄やラメは避ける
子どもの服装
子どもには大人ほど厳格なマナーは求められませんが、できるだけ場に合った装いを心がけましょう。
- 黒・紺・グレーなどの落ち着いた色合いの服
- 男の子:白シャツ+黒や紺のズボン(学校の制服があれば可)
- 女の子:白ブラウス+地味なスカート/ワンピース
- 靴下・靴もなるべく黒または落ち着いた色を選ぶ
小さな子には着心地や動きやすさも考慮しつつ、「派手すぎない」を基準にすれば問題ありません。
ただし、服装のトーンや雰囲気は、地域や宗派、家の慣習によっても異なるため、事前に確認しておくと安心です。
数珠・香典の準備
数珠は必須アイテムです。宗派によって持ち方が違うこともありますが、持っているだけでも丁寧な印象を与えます。
香典の表書きには、
- 御仏前
- 御霊前
- 御供
などがありますが、四十九日以降は「御仏前」が一般的です。
中袋には必ず名前と金額を明記しましょう。香典袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。渡すときはふくさから出して、両手で丁寧に手渡します。
遅刻・欠席時のマナー
やむを得ず遅れる場合は、必ず事前連絡をしましょう。静かな読経の最中に入室することがないよう、時間には余裕を持って到着したいものです。
欠席する場合でも、香典を郵送するなどの配慮をし、メッセージを添えると、丁寧な印象になります。
よくある法事の疑問Q&A

ここでは、法事についてよくある疑問と、その回答をまとめました。
Q1.法事は必ずやらないといけない?
結論からいえば、法律上の義務はありません。
しかし、日本では仏教をベースにした供養の習慣が根づいており、親族や地域の慣習によって「やるべきもの」とされるケースが多くあります。
特に、一周忌や三回忌までは丁寧に行う家庭が多いため、急に省略すると、親族間で誤解を生むこともあるため、気をつけましょう。
「形式より気持ち」が基本とはいえ、親族とよく相談し、みんなが納得できる形を選ぶのが大切です。
Q2.法事は何回忌までやればいい?
昔は、三十三回忌まで丁寧に行うのが通例でしたが、現代では簡略化されることが増えています。
一般的には、次のような考え方が多くなっています。
- 一周忌・三回忌まで:しっかり行う
- 七回忌以降:親族だけで簡素に行う、または省略する
- 十三~三十三回忌:地域や家の方針で対応する
親族の高齢化や、距離の問題もあるため、「どこで区切るか」も、家族で話し合って決めるのが望ましいです。
Q3.法事は仏滅の日にやるもの?
「仏滅=仏に縁がある日だから法事に適している」というのは、実は誤解です。
仏滅は「六曜(ろくよう)」という「暦注(れきちゅう)」の一種で、占いのようなもの。仏教とは無関係です。
そのため、法事を仏滅に行っても何の問題もありません。いつ行っても良いものです。むしろ、斎場やレストランの予約が取りやすいという実用面での利点もあります。
ただし、仏滅であることを、年配の親族が気にされる場合もあるため、日程を決める際は一言相談しておくと、トラブルを避けられます。
Q4.料理や引き出物はどんなものを用意すればいい?
法事の会食では、和食のコース料理が一般的です。
精進料理にこだわる必要はなく、最近では肉や魚を含むメニューも増えています。
重要なのは「故人を偲びながら、静かに語り合う場」としてふさわしい内容であることです。
引き出物には、
- 焼き菓子
- 海苔・お茶
- タオル・洗剤セット
など、日持ちする消耗品や日用品が選ばれることが多いです。
地域や年齢層に合わせて選ぶと、より喜ばれるでしょう。
まとめ
法事とは、故人の冥福を祈り、家族や親族が集まって心を通わせる、大切な供養の行事です。
仏教の教えに基づいたこの習わしには、故人の魂を安らかに送り出すという意味がある一方で、残された人々が故人を偲び、感謝の気持ちをかたちにするという役割もあります。
法事には、読経を中心とした「法要」に加え、焼香や会食、引き出物の準備など、さまざまな段取りがあります。特に、一周忌や三回忌など、節目の年には丁寧に行われることが多く、地域の習慣や家族の考え方に合わせて進めていくことが大切です。
近年では、家族の状況や参列者の都合を考慮して、法事の内容を簡略化するご家庭も増えています。ですが、形式にとらわれるよりも、「故人を思う気持ち」が何よりも大切だということを忘れずにいたいものです。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。