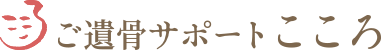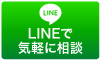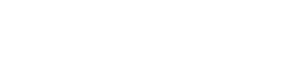ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
閉眼供養のお供え物は何がいい?注意点やマナーについて解説
仏壇を処分する時や、墓じまいを行う際に必要となるのが閉眼供養です。閉眼供養は、仏壇やお墓に宿ったご先祖様の魂をお送りする、非常に大切な儀式です。
しかし、普段なじみのない供養だけに、「何を持っていけばいいの?」「お供え物のマナーってあるの?」と迷う方も少なくありません。
そこで今回は、閉眼供養にふさわしいお供え物の種類や意味、選ぶ際の注意点、当日のマナーまでをわかりやすく解説します。
終活や永代供養を検討されている方にも、役立つ情報をまとめていますので、どうぞ最後までご覧ください。
Contents
閉眼供養とは?意味や目的を知っておこう
そもそも閉眼供養とはどのような儀式なのか、簡単に概要を説明します。
「閉眼」の本来の意味とは
「閉眼(へいがん)」という言葉には、仏像や位牌、仏壇、お墓などに宿った魂を、お還しするという意味があります。
通称「魂抜き」「お性根抜き(しょうねぬき)」とも呼ばれ、これらの対象がもはや「礼拝の対象ではなくなる」前に、丁重に魂を抜くための儀式が必要とされるのです。
仏教の考え方では、仏壇やお墓にはご先祖様の魂が宿るとされており、それらを勝手に処分したり、移動したりすることは避けるべきとされています。
「ただの物」ではなく、「魂の宿る場所」として扱ってきたものを閉じるにあたり、きちんと仏様に「今までありがとうございました」とお伝えし、供養する。それが閉眼供養の目的です。
このように、閉眼供養は単なる儀式ではなく、感謝と区切りを表すための大切な法要なのです。
墓じまいや引っ越しの際に必要な供養
では、どのような場面で閉眼供養が必要になるのでしょうか?
代表的なのは、「墓じまい」を行うときです。
たとえば、代々守ってきたお墓を維持するのが難しくなり、永代供養墓に移す場合や、ご遺骨を納骨堂に移す場合などに墓じまいを行いますが、その際に閉眼供養が必要です。
または、仏壇を処分したり、別の場所に移動させたりする場面でも、同様に閉眼供養を行なってから、移動します。
閉眼供養をせずに仏壇や墓石を処分してしまうことは、仏教的な意味合いだけでなく、心の整理という観点からもおすすめできません。
ご先祖様に感謝の気持ちを伝え、自分自身もきちんと「区切り」をつける。その役割を担っているのが閉眼供養なのです。
閉眼供養に必要なお供え物とは

閉眼供養を行う際は、お供え物を用意します。お供え物の種類やそれぞれの意味について、解説します。
五供とは?仏様にお供えする5つの基本
閉眼供養でお供え物を準備する際の基本となるのが、「五供(ごくう)」と呼ばれる5つの供物です。
五供とは、仏教において仏様を敬い、感謝の気持ちを表すために供える「香・花・灯明・水・飲食」のこと。これは仏壇供養にも通じる、供養の基本的な考え方であり、閉眼供養の場でも欠かせないものとされています。
これらをそろえるのは、単なる形式ではありません。仏様に向き合い、心を整える行為そのものに、大きな意味が込められているのです。
仏教では、供養という行為そのものが「功徳(くどく)を積む」とされ、真心を込めて準備されたお供え物には、故人への敬意と遺族の想いがにじみ出るとされています。
特に閉眼供養は、「これまでこの場を守ってくださり、ありがとうございました」という感謝と、「新たな場所で安らかに過ごしてください」という祈りを込める、重要な節目。
そうした想いを形にするためにも、五供を意識した丁寧な準備が大切です。
お供え物のそれぞれの役割と意味
ここでは、五供それぞれが持つ意味や、選び方のポイントについてご紹介します。
<香(こう)>
仏教において香は「心を清めるもの」とされます。
お線香や抹香を焚くことで、空間を浄め、仏様や故人に安らぎを届けるとされており、閉眼供養でも必須の供物です。空間だけでなく、人の心まで清めてくれるもので、供養には欠かせません。
香の香りは邪気を祓うともいわれており、供養の場を神聖な空間へと導きます。
できれば香りが強すぎない自然な白檀(びゃくだん)系や沈香(じんこう)系のものを選ぶとよいでしょう。
<花(供花・くげ)>
花は「仏様への敬意と美しさの象徴」です。
故人の好みに合わせて用意することもありますが、基本的には白を基調とした落ち着いた生花がふさわしいとされています。
香りの強いユリや、色の濃すぎる花は避けるのが一般的なマナーです。
<灯明(とうみょう)>
灯明とは、ローソクの明かりのことを指し、「仏様の智慧を象徴する光」です。暗闇を照らし、道を示す光でもあり、魂の旅立ちを導く意味もあります。
供養の場では、ローソクを灯すことで仏の教えと故人の魂に祈りを捧げる意味を込めます。
最近では、風で消えにくい、LED灯明も用いられるようになってきました。火を使わず、安全です。
<水(すい)>
水は「清浄の象徴」です。
雑味のない清らかな水を供えることで、心の浄化や穢れの除去を表します。
毎朝入れ替えるという家庭もあるほど、水は仏前において、非常に神聖な存在とされています。
閉眼供養の際には、透明なガラス器や小さな杯に冷たい水をそっと注ぎ、仏前に供えましょう。
<飲食(おんじき)>
飲食とは、ご飯や果物、お菓子などのことです。故人が生前好きだったものを供えると、喜んでもらえるとされています。
ただし、閉眼供養の場では香りの強いものや生ものは避けるのがマナーです。
また、地域によっては赤飯や季節の果物を供える習慣があるところもあります。迷ったら、お寺や親戚と相談すると良いでしょう。
無理に豪華なものを用意する必要はなく、心を込めて選ぶことが何よりも大切です。
閉眼供養のお供え物を選ぶ時の注意

閉眼供養では、仏様や故人に敬意を払った「ふさわしいお供え物」を選ぶことが大切です。
供養の場に不適切なものを供えてしまうと、周囲の人に不快な印象を与えてしまうだけでなく、仏教の教義や風習に反する行為となることもあります。
ここでは、閉眼供養のお供え物を選ぶ際に気をつけておきたい3つのポイントをご紹介します。
生ものなど傷みやすいものは避ける
まず注意したいのが、保存性の低い食べ物を避けることです。
閉眼供養は野外(お墓)で行われることも多く、季節や気温によってはお供えした食べ物がすぐに傷んでしまうことがあります。
たとえば、
- 生魚
- 生クリームを使ったケーキ
- カットした果物
などは腐敗しやすく、虫が寄ってくる原因にもなりかねません。
また、供養が終わったあとにその場で食べる(供食する)ことを考えても、傷みやすいものは避けた方が無難です。
代わりに、日持ちのする果物(リンゴやみかん)、個包装された和菓子や焼き菓子などがおすすめです。
故人が好きだった食べ物を供えることもありますが、保存性や場の雰囲気に配慮したうえで選ぶようにしましょう。
五辛(ごしん)に該当する食材は避ける
仏教では、「五辛(ごしん)」と呼ばれる5つの刺激物を供養の場で避けるべきとされています。
五辛とは、
- ニラ
- ネギ
- ニンニク
- ラッキョウ
- アサツキ
などの、臭いや刺激が強い野菜のことを指します。
これらは古くから「修行や瞑想の妨げになる」とされており、仏前に供える食べ物としては不適切と考えられています。
たとえ加熱調理されていたとしても、五辛を含む料理は避けるのが基本です。
たとえば、ニンニク入りの餃子や、ネギたっぷりの料理などは、たとえ故人の好物であっても閉眼供養の場では控えた方がよいでしょう。
故人への思いを大切にしながらも、仏教の教えや儀式の厳粛さを、尊重する姿勢が大切です。
香りが強すぎる花や派手な花はNG
供花を用意する際にも、気をつけたいポイントがあります。
特に注意したいのが、香りの強すぎる花や、色が派手で仏前にふさわしくない花です。
たとえば、ユリやカラーは見た目が美しい反面、香りが強く、体調によっては不快に感じる人もいます。
また、真紅のバラやビビッドな南国系の花も、供養の場にはふさわしくないとされることが多いです。
仏前に供える花としては、
- 菊
- カーネーション
- トルコキキョウ
など白を基調とした淡い色合いの花が一般的で、落ち着いた雰囲気を大切にします。
ただし、地域や宗派によって考え方に違いがあるため、不安な場合は事前にお寺や親族に確認しておくと安心です。
閉眼供養の際のお供え物のマナー

お供え物を用意するだけでなく、「どのように供えるか」も大切なマナーのひとつです。
閉眼供養は、仏壇やお墓に宿った魂を、丁重にお送りする重要な儀式。だからこそ、供え方や儀式後の取り扱いにも、心を配りたいものです。
ここでは、当日に戸惑うことのないよう、基本的なお供え物のマナーを解説します。
お供え物の正しい置き方
閉眼供養のお供え物は、「仏様や故人に向けて丁寧に供える」という意識を持つことが大切です。
まず、お供え物を墓石に直接おくことはしません。懐紙やお盆などを用意しておきましょう。
そして、墓前に向かって、故人から見て正面になるように配置するのが基本です。たとえば、お菓子や果物をお供えする場合は、包装やラベルが見える向きではなく、中身の表面を故人に向けるように並べます。
供花は、左右対称に並べると美しく、また仏教の作法としても調和が重視されます。
灯明(ろうそく)は、供養が始まる直前に点灯し、儀式が終わったら安全に消すようにしましょう。
なお、お供え物の種類や配置の作法は、宗派によって微妙に異なることがあります。
不安な場合は、事前に菩提寺や葬儀社に相談しておくと安心です。
閉眼供養が終わった後のお供え物の取り扱い
供養が終わったあと、お供え物をそのまま放置するのは、マナー違反とされています。
とくに、屋外で行われるお墓の閉眼供養では、動物や虫が寄ってきたり、腐敗してしまったりするため、速やかに片づけるのが基本です。
仏教では「供養したものは、故人と分かち合うようにいただく」という考え方があります。
そのため、日持ちする食べ物やお菓子は、親族や参列者で分けていただく(=供食する)のが一般的です。
食べられないものや、持ち帰りが難しいものは、必ずごみとして処分する前に感謝の気持ちを込めて手を合わせ、「ありがとうございました」と声をかけてから片づけるとよいでしょう。
また、持ち帰る際は、「仏前にお供えしたものを持ち帰るのは気が引ける」と感じる方もいますが、これは失礼にはあたりません。
むしろ、丁寧に供え、丁寧に持ち帰ることが、供養の一環とされています。
お供え物以外に用意しておきたい持ち物

閉眼供養では、お供え物の準備に目が向きがちですが、当日スムーズに儀式を進めるためには、他にもいくつか持っておきたいアイテムがあります。
特に屋外で行う墓じまいや、慣れない場所での供養では、ちょっとした持ち物の有無が安心感にもつながります。事前に、持ち物チェックリストを作っておくと良いでしょう。
ここでは、閉眼供養に参列する際にあると便利な持ち物を、用途別にご紹介します。
1. 数珠(じゅず)
仏教の供養儀式では欠かせない必需品です。読経や焼香の際に手にかけることで、気持ちが整い、所作も自然と丁寧になります。
宗派によって形が異なることもありますが、一般的な略式の数珠でも問題ありません。
2. 線香・ライター
お寺や石材店が用意してくれることもありますが、念のため自分でも持参すると安心です。
風のある屋外では火がつきにくいこともあるため、風防付きのライターがあると便利です。
3. ハンカチ・ティッシュ
感情がこみ上げて涙が出ることもありますし、手を拭く場面もあります。
あらたまった場でも使えるよう、落ち着いた色味の布製ハンカチを用意しておくのがおすすめです。
4. 小銭(お布施袋とは別に)
お墓や寺院へのお参りの際に、賽銭として使うことがあります。
現地で突然必要になることもあるため、100円玉や10円玉などを数枚用意しておくと安心です。
5. 防寒具・日除けアイテム(季節に応じて)
夏の屋外供養では、日傘・帽子・冷却タオルなどが役立ちますし、冬であればカイロ・マフラー・手袋などを忘れずに持っていきましょう。
儀式中は長時間屋外で立つこともあるため、体調管理のための持ち物は意外と重要です。
6. 替えのマスク・携帯用ごみ袋
コロナ禍以降、供養の場でもマスクの着用が推奨される場面があります。
また、お供え物の包装紙などをその場で持ち帰るためにビニール袋があると便利です。
7. お布施袋(のし袋)
お布施は封筒に入れ、あらかじめ「御布施」と表書きをし、ふくさに包んで持参するのがマナーです。
そのためののし袋やふくさも忘れずに用意しておきましょう。
閉眼供養の流れ

閉眼供養は、仏壇やお墓に宿る「魂を閉じる」という非常に大切な儀式です。
一般的には僧侶(お寺の住職)にお願いして読経をしてもらい、魂抜きの作法を経て、仏壇の処分や墓じまい、納骨先の移動へと進みます。
ここでは、事前にやっておくべき準備と、当日の一般的な流れについて詳しくご紹介します。
墓地や仏壇の掃除は事前に済ませる
閉眼供養を行う前に、供養の対象となる場所や物をきれいにしておくことが大切です。
お墓の場合は、墓石の水垢や苔を丁寧に落とし、雑草を取り除きます。仏壇であれば、中の仏具を拭き、埃を払って整えておくとよいでしょう。
これは単なる見た目の準備ではなく、感謝と敬意の気持ちを表すためでもあります。
「これまで守っていただき、ありがとうございました」という想いを込めて、丁寧に整えておくことが、供養の第一歩です。
僧侶への挨拶と進行の確認
当日、僧侶が到着されたら、まずは丁寧にご挨拶をしましょう。
僧侶が複数の供養を掛け持ちしている場合もあるため、時間や供養の流れを、事前に確認しておくことが大切です。
その際には以下のような内容を確認しておくと安心です。
- 読経にかかるおおよその時間
- お供え物の配置やタイミング
- 写真撮影が可能かどうか(親族用の記録として)
また、時間があれば、「本日はよろしくお願いします」という気持ちを込めて、このタイミングでお布施をお渡ししておきましょう。
供養の流れ(読経 → お供え → 魂抜き → 骨の取り出し)
閉眼供養の中心となるのは、僧侶による読経です。
般若心経などが読まれ、故人やご先祖様の魂が浄化されるよう祈りが捧げられます。この間、遺族は静かに手を合わせ、心を整えて故人との別れに向き合います。
読経の途中または終了後に、お供え物を仏前または墓前に丁寧に配置します。
この際に、あらかじめ準備しておいた五供を中心に、故人の好物なども添えるとよいでしょう。
読経が終わると、順番に焼香を行います。仏壇であればこの後に処分が可能となり、お墓であれば「ご遺骨の取り出し」や墓石の撤去へと進むことになります。
なお、ご遺骨を取り出した後は、永代供養墓や納骨堂への改葬(かいそう)、または手元供養に移るケースもあります。
閉眼供養は、これら「供養の次のステージ」へ進むための大切な区切りでもあるのです。
閉眼供養にお布施は必要?

閉眼供養は、僧侶に読経をお願いする正式な法要のひとつです。そのため、お布施を用意するのが一般的なマナーとされています。
ここでは、お布施の目安金額や渡し方、石材店など他の関係者への「心付け」についても解説します。
僧侶にお渡しするお布施の目安と相場
お布施とは、僧侶への感謝の気持ちを「お金という形で表すもの」であり、単なる「料金」や「報酬」とは異なります。
金額に明確な決まりはありませんが、失礼のない範囲で適切に包むことが大切です。
閉眼供養におけるお布施の相場は、地域やお寺によっても異なりますが、おおむね3万円~10万円程度が一般的です。
供養の内容や所要時間、僧侶との関係性(菩提寺かどうか)によっても上下します。金額で迷ったら、お寺に直接聞いてみても良いでしょう。
お布施の他に、以下のような別途費用が発生する場合もあります。
- 御車代:僧侶の交通費として。5,000円~1万円程度
- 御膳料:会食に参加されない場合。5,000円~1万円程度
これらはお布施と分けて、それぞれの封筒に「御車代」「御膳料」と表書きするのが丁寧な作法です。
また、お布施は白無地の封筒または仏事用の「のし袋」に包み、ふくさに入れて持参するのが正式なマナー。表書きは「御布施」とし、水引きは黒白または双銀の結び切りを選びましょう。
石材店への心付け
閉眼供養の後、墓じまいを依頼する場合は、石材店などの業者に墓石の撤去作業をしていただきます。もちろん、作業費用はきちんと支払っているので、必ずしも追加でお礼を渡す必要はありません。
ただ、夏の炎天下での作業や、冬の寒い日に作業をしてもらった時など、お礼をお渡ししたいと思ったときに、「ありがとうございます」という気持ちを込めて、お渡しするのは差し支えないでしょう。
相場は、作業内容や人数にもよりますが、3,000円~1万円程度が目安です。複数人で作業される場合は、人数分を個別に封筒に包んで渡すと丁寧です。
心付けに使う封筒は、あまり仰々しくない白い無地の封筒でかまいません。
表書きは
- 御礼
- 心付け
- 志
などが使われます。
なお、石材店によっては「心付けはご遠慮しています」と事前に断られる場合もあるため、事前の確認が必須です。
閉眼供養の時の服装のマナー

閉眼供養は、仏壇やお墓の区切りをつける厳かな儀式です。派手すぎる服装やカジュアルすぎる服装は避け、仏前にふさわしい落ち着いた服装で臨むことが大切です。
ここでは、閉眼供養の際にふさわしい服装の基本と、季節ごとの注意点を解説します。
喪服またはダークフォーマルが基本
閉眼供養においては、葬儀ほど厳密ではないものの、基本的には準喪服、または略式喪服レベルの服装が好ましいとされています。
黒・紺・グレーなどのダークカラーを基調としたフォーマルな服装が適切です。
<男性の場合>
- 黒または濃紺のスーツ
- 白いシャツ
- 黒いネクタイ・黒の靴下・黒の革靴
<女性の場合>
- 黒や濃紺のワンピース、スーツ、またはアンサンブル
- 肌の露出が少ないもの(ノースリーブ・ミニ丈は避ける)
- 黒いパンプス、ストッキングは肌色または黒の無地
アクセサリーは控えめにし、真珠のネックレス1連程度が一般的です。光沢の強いものや大ぶりな装飾は避けましょう。
バッグも黒で、布製かつ金具の目立たないものがベストです。
季節に応じた羽織や日除けも準備
閉眼供養は屋外で行われることも多く、季節や天候への対策も大切なマナーの一部です。
<夏場の対策>
- 黒や紺など落ち着いた色の日傘(※白やレースは避ける)
- 汗をかいても目立ちにくい素材の服
- ハンドタオルや扇子などの暑さ対策グッズ
<冬場の対策>
- ダークカラーのコートやジャケット(派手なデザインは避ける)
- 黒い手袋・マフラー・カイロなど防寒アイテム
どの季節でも、屋外に長時間立つことを想定した服装を心がけましょう。
特に高齢のご親族がいる場合は、折りたたみ椅子やひざ掛けを用意しておくと喜ばれます。
まとめ
閉眼供養は、仏壇やお墓に宿った魂をきちんとお送りする、人生の節目にふさわしい大切な供養です。
ただ形式的に済ませるのではなく、故人やご先祖様への感謝の気持ちを込めて丁寧に行うことが、何より大切といえるでしょう。
お供え物には五供を意識し、生ものや五辛、香りの強い花を避けるなど、マナーや仏教の教えに沿った配慮が大切です。
また、当日の服装や持ち物、供養後のお布施の準備までを含め、全体の流れをあらかじめ把握しておくことで、安心して当日を迎えることができます。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。