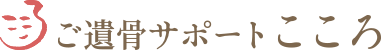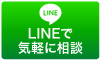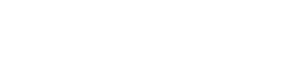ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者
墓じまいをしないとどうなる?お墓の放置が招くリスクとは
核家族化が進み、お墓の管理が難しいと感じている人は増えていますが、ではお墓をどうしたら良いのかわからず、放置してしまっている人も多いのではないでしょうか。
しかし、お墓を放置することで未来の家族や子孫に大きな負担をかけることになりかねません。
そこで今回は、墓じまいをしないとどうなるのか、考えられるリスクやその回避方法について詳しく解説します。お墓問題でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
墓じまいをしないとどうなる?ご遺骨の行方
墓じまいをせずにお墓を放置すると、ご遺骨がどうなるのかは墓地の種類によって異なります。公営墓地・霊園、民営墓地・霊園、寺院墓地のそれぞれのケースを解説します。
公営墓地・霊園ではそのまま放置されることが多い
自治体が管理する公営墓地では、利用者が墓じまいをしない限り、基本的にそのまま放置されることが多いです。
ただし、管理費が長期間未納になると「無縁墓」とみなされ、一定期間の公告の後に撤去・合祀されることもあります。自治体ごとに対応が異なるため、事前に確認が必要です。
民営墓地・霊園では撤去される可能性がある
民営墓地の場合、管理会社が運営しているため、管理費の未納が続くと墓地の使用権を失い、撤去される可能性があります。
撤去された後のご遺骨は、管理者の判断で合祀墓に納められることが多いです。家族の意向を確認してくれるとは限りませんので注意しましょう。
寺院の墓地では合祀されることが多い
寺院の墓地では、墓じまいをせず管理費を支払わないと「無縁仏」と判断され、ご遺骨が合祀墓(合同供養塔)に移されることが一般的です。
合祀されると、後から遺骨を取り出すことは困難になり、個別の供養はできなくなってしまいます。
1999年の法改正によってお墓の撤去が可能となった
1999年の法改正は、墓埋法の一部を改正したものです。お墓の承継者がいない場合や、管理費が長期間滞納されている場合など、一定の条件を満たせば、墓地管理者が墓地を廃止し、墓石を撤去したり、納骨されている遺骨を取り出すことができるようになりました。
撤去までの流れは以下の通りです。
1.管理料の未納が続き、墓地管理者が「無縁墓」と判断する
長期間、管理費が支払われず、墓参りなどの管理がされていない墓は「無縁墓」とみなされる可能性が高くなります。
2.一定期間の公告を行う
墓地管理者は、墓の継承者を探すために、官報や墓地内の掲示板などに公告を掲載し、一定期間、継承者の申し出を待つ必要があります。
3.期限内に継承者が名乗り出なければ、お墓を撤去できる
公告期間が過ぎても継承者から連絡がない場合、墓地管理者は墓を撤去し、ご遺骨を合祀墓(合同供養塔)などに移すことが可能になります。
放置された状態が続くと、無縁墓とみなされる可能性が高くなります。お墓の持ち主は、墓じまいをするか、それとも墓地の管理費を支払い続けるか、どちらか選択しなくてはなりません。
将来的にお墓を継ぐ人がいない場合は、墓じまいを行い、永代供養や散骨などの方法を選ぶことをおすすめします。
墓じまいをしないことで生じるリスク

墓じまいをしないまま放置すると、さまざまな問題が発生する可能性があります。
お墓が荒れる
長期間放置されたお墓は、雑草が生い茂り、墓石が劣化してひび割れたり、倒壊したりする恐れがあります。
墓地の清掃や手入れが行き届かなくなり、荒れた状態が続くと、カラスや動物による荒らしの原因にもなります。周囲の景観を損ねるだけでなく、他の墓参者にも迷惑をかけてしまうでしょう。
いずれ無縁墓となって撤去される
お墓の管理をする人がいなくなった場合、墓地管理者が「無縁墓」と判断し、一定の手続きを経て撤去されることになります。
撤去されたご遺骨は、合祀墓などに移されることが一般的です。合祀墓に移されると、ご遺骨を個別に取り出すことが難しくなるため、家族の意向に沿った供養ができなくなる可能性があります。
管理費等の負担
お墓を所有している限り、管理費などの維持費が発生し続けます。墓じまいをせずに放置すると、管理費の支払いが滞り、墓地管理者から督促を受けることがあります。
特に寺院墓地では、管理費のほかに法要費用や寄付金が発生するケースが多く、子孫に大きな経済的負担を残すことになります。
菩提寺と檀家の関係悪化
お墓が寺院墓地にある場合、墓じまいをせずに放置することで、菩提寺との関係が悪化する可能性があります。
寺院との関係が悪化すると、将来的に法要や供養を頼みにくくなり、他の親族にも影響を及ぼす可能性があります。
お墓を管理できないのに墓じまいしない理由

お墓の管理ができなくなったにもかかわらず、墓じまいが進まないケースは少なくありません。その理由としては、以下のような状況が考えられます。
お墓の継承者が誰だかわからなくなっている
現代では、核家族化や少子化の影響で、お墓の継承がスムーズに行われないケースが増えており、特に親族関係が希薄になっている場合、お墓の継承者が誰なのかわからなくなっていることがあります。
転居や引っ越しを繰り返すうちに、親族との連絡が途絶えてしまい、お墓の存在を誰も把握しておらず、継承者に関する情報が不明になることもあります。
墓じまいの費用を用意できない
墓じまいには一定の費用がかかるため、金銭的な負担が理由で手続きが進まないこともあります。
墓石の撤去は、10万円~30万円程度が相場ですが、墓地の広さや石材の種類によっても違ってきます。
また、墓じまいをした後の供養の方法によっては、さらに費用がかかるため、これらの費用をすぐに用意できない場合があります。
お墓があることを認識していない
意外に多いのが、そもそもお墓の存在を知らずに放置されているケースです。先祖代々の墓が遠方にあると、親族の間で話題にすら上がらないこともあります。
お墓参りに行く習慣も少なくなっているため、お墓の存在を意識することがなくなっている家庭は増えています。
墓じまいをした方が良い人

墓じまいをすべきかどうかは、個々の状況によって異なりますが、以下のような状況に当てはまるなら、墓じまいをした方が良いでしょう。
お墓の継承者がいない
子どもがいない、または親族に引き継ぐ人がいない人、または、親族がいても、お墓を管理する意思や余裕がない人は、墓じまいをした方が良いです。
親族が遠方に住んでおり、定期的な管理が難しい場合も同様です。継承者がいなくなると、お墓の管理が滞り、荒廃が進んでしまう可能性が高いため、親戚がまだたくさん残っているうちに、話し合った方が良いでしょう。
お墓が遠方にあって管理が難しい
お墓が自宅から遠く離れた場所にある場合、墓参りや清掃が困難になります。高齢になると、遠方への移動が難しくなり、お墓の管理がますます困難になるでしょう。
遠方のお墓は、交通費や移動時間の負担が大きいです。
親族間で管理の押し付け合いが発生することもありますから、早めに自宅近くの納骨堂や永代供養墓へ移すことで、管理しやすくなります。
子供や孫に負担をかけたくない
子供や孫が遠方に住んでいる場合、お墓の管理や墓参りの負担をかけてしまう可能性があります。
お墓の継承者がわからない場合、将来的に墓じまいをするときに、子どもや孫が高額な費用を負担しなければならなくなります。
自分が元気なうちに墓じまいを行い、負担を次世代に残さないことも大切です。
管理費の負担など経済的に厳しい場合
墓地や霊園によっては、年間管理費がかかります。管理費の支払いが経済的な負担になっている場合、墓じまいを検討した方が良いでしょう。
墓じまいには費用がかかりますが、長期的に見ると管理費の負担を軽減できます。
墓じまいの進め方

墓じまいは、単にお墓を撤去するだけでなく、遺骨の行き先を決め、寺院や墓地管理者との調整など、いくつものステップを踏む必要があります。
ここでは、墓じまいの基本的な流れを順番に詳しく解説します。
家族や親族と墓じまいについて相談する
まず、家族や親族と話し合いを行い、墓じまいの意向を共有することが大切です。墓じまいは先祖代々のお墓を撤去することになるため、家族間で意見が分かれることがあります。
- 管理が困難
- 継承者がいない
- 経済的負担
など墓じまいの理由や目的を共有します。
特に遠方に住んでいる親族や親戚の意向も確認することが大切で、全員が納得できる形を目指しましょう。
費用負担についても話し合い、後々のトラブルを防ぎます。
次の供養の方法を決める
墓じまいをした後、ご遺骨をどこで供養するかを決める必要があります。以下のような選択肢があります。
- 永代供養墓:寺院や霊園が管理する共同墓。管理不要で費用が比較的安い
- 納骨堂:屋内施設に遺骨を安置する形式で、アクセスしやすい場所を選べる
- 樹木葬:自然に還る供養方法。費用が抑えられ、宗教不問のことが多い
- 散骨:海や山に遺骨を撒く方法
- 手元供養:遺骨の一部を自宅で供養する。遺族が自由に供養できる
家族や親族の意向を尊重し、最適な供養方法を選びましょう。
ご遺骨を管理しているところに連絡をする
お墓がある寺院や霊園、自治体の管理者に連絡し、墓じまいの意向を伝えます。
寺院に墓地がある場合、檀家をやめる手続きが必要です。離檀料を求められることがあるので、事前に確認しましょう。
いきなり墓じまいをしますと申し出るよりも、お墓の管理が難しくなってきたからと、「相談」する形にすると、角が立ちにくいでしょう。
墓じまいの時期や工事の日程についての調整も必要です。
行政手続きをする
ご遺骨を別の場所へ移す場合、改葬許可申請が行政手続きが必要です。
- 現在の墓地管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう
- 新しい供養先(納骨堂・永代供養墓など)の「受入証明書」を取得する
- 現在のお墓がある市区町村に「改葬許可申請書」を提出する
- 改葬許可証が発行される
この「改葬許可証」がないと、遺骨を移動することができません。申請に必要な書類を事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
石材店に工事を依頼する
墓石を撤去するために、墓じまい専門の石材店に工事を依頼します。墓地によっては、指定業者が決まっている場合があるため、事前に管理者に確認が必要です。
費用の相場は10万~30万円程度ですが、もし業者を自由に選べるなら、事前に見積もりを取り、費用を比較すると良いでしょう。
ご遺骨を取り出して墓地を返還する
工事の日程が決まったら、お墓の閉眼供養(魂抜き)を行い、ご遺骨を取り出します。無宗教の場合は、お墓の前で手を合わせ、感謝の気持ちを伝えるだけでも大丈夫です。
墓石を撤去したら、墓地は更地に戻し、霊園や寺院に返還します。
墓じまいにかかる費用の目安

墓石の大きさや数、石の種類、撤去作業の難易度によって費用が異なります。10万円~30万円程度が一般的ですが、大きいと50万円ほどかかることもあります。
そのほかにかかる費用は、以下の通りです。
- 離檀料:数万円~20万円
- 行政手続き費用:数千円
- 新しい納骨先の費用:10万円~300万円
新たにお墓を建てようとすると、数百万円かかる場合もあります。
費用を抑えたい場合は永代供養墓や手元供養、散骨などを検討します。
墓じまいの費用が払えない場合はどうする?
墓じまいには最低でも20万円程度、場合によっては数百万円の費用がかかることがあります。もし支払いが難しい場合、以下の方法で負担を軽減できる可能性があります。
家族、親族に相談する
墓じまいは一人で負担するものではなく、親族と協力して進めることが大切です。昔のように、長男の家だけが負担する必要はありません。以下のような点を話し合いましょう。
- 兄弟・親戚と負担を分けるなどして費用を分担できないか
- 他の親族がお墓を継承できないか
- 家族内で協力して一時的にお金を借りることができないか
もしかしたら、話し合いの結果、管理できる人がいるかもしれません。そうなれば、墓じまいをしなくても済みます。
墓じまいが決定したなら、費用は一人で負担せず、できるだけ協力して費用を分担することをおすすめします。
墓地の管理者に相談する
寺院や霊園など墓地の管理者に事情を説明すると、分割払いを認めてもらえる場合や、負担を軽くする方法を提案してもらえることがあります。
寺院墓地の場合、墓じまいをする代わりに永代供養へ移行できることもあるため、早めに相談してみましょう。
自治体に補助金制度がないか調べてみる
一部の自治体では、墓じまいの費用に対する補助金制度を設けています。お住まいの自治体の窓口やホームページで、補助金制度の有無を確認してみましょう。
全ての自治体に補助制度があるわけではありませんが、一度調べてみる価値はあります。
メモリアルローンを利用する
墓じまい専用のローン(メモリアルローン)を利用することで、費用を分割で支払うことが可能です。審査があるため、必ず借りられるとは限りませんが、銀行系のローンは比較的低金利でおすすめです。
ローンを利用する際は、金利や返済期間などを比較検討し、無理のない返済計画を立てましょう。
墓じまいをした後のご遺骨の供養の方法

墓じまいをした後、ご遺骨をどのように供養するかを決める必要があります。現在では、従来のお墓にこだわらない供養方法も増えており、ライフスタイルや費用に応じて選択できます。
永代供養墓
お寺や霊園が管理し、個人や家族の代わりに永続的に供養してくれるお墓です。基本的に管理費不要で、後継者がいなくても供養が続くため、多くの人が選ぶ方法です。
通常のお墓より費用が安いのも、大きなメリットです。合祀される場合が多いので、他の方とご遺骨が混ざってしまうことに抵抗がある人には向いていません。
樹木葬
墓石の代わりに樹木を墓標とする供養方法です。自然に還るという考え方から、近年人気が高まっています。墓石が不要で比較的安価です。
永代供養が付いている場合が多く、継承者がいなくても供養を任せられるので安心です。
納骨堂
遺骨を建物内に安置する供養方法で、ロッカー式・仏壇式・自動搬送式(ICカードで参拝)などの種類があります。屋内にあるため、天候に関係なくお参りしやすいのが特徴です。
一般のお墓より費用が安く、都市部にあることが多いので、アクセスしやすいのもメリットの一つです。
散骨
遺骨を粉状にして海や山など自然に撒く供養方法です。専門の業者に依頼して、船をチャーターして沖まで出てご遺骨を撒いたり、散骨専用の山林で撒いたりします。
法律上は、節度を持って行えば散骨自体はなんら問題ありませんが、観光地など、場所によっては条例による制約があるため注意が必要です。
手元供養
遺骨を骨壺やアクセサリーに納め、自宅で供養する方法です。お墓や納骨堂を持たず、身近に故人を感じられるとして人気があります。
遺族間で意見が分かれることがありますが、分骨して、納骨と併用も可能です。
まとめ
墓じまいをしないまま放置すると、お墓の荒廃や無縁墓としての撤去、管理費の負担増加などのリスクが発生します。
公営墓地ではそのまま放置されることが多い一方、民営墓地では撤去される可能性があり、寺院墓地ではそのまま合祀されてしまうこともあります。
継承者がいない場合や経済的負担が大きい場合には、家族や親族と相談し、永代供養墓や納骨堂、散骨など、現代のライフスタイルに合った供養方法を検討することが重要です。
墓じまいは一時的な費用がかかるものの、将来的な負担を軽減し、故人を適切に供養するための大切な選択肢の一つです。
この記事の監修者

天井 十秋
大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。
ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。
ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。
ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。